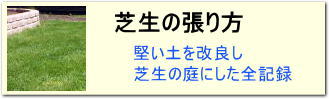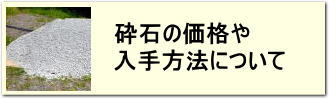大型のふるいを自作 キャスターを利用して楽に手動で動かすタイプです

庭に芝生を植えるため、床土を改善する必要がありました。
そのために、もともと石混じりの堅い土を掘り起こし、ふるいにかけて石や根っこを取り除いてから埋め戻す必要があるのですが、この「ふるい掛け」を効率良くやるために、どうしても大型のふるい機が必要なので、自作しました。
キャスター(固定タイプ)を4個使用し、出来るだけ楽に動かせるようにしています。
大型ふるいを作る

作業台の上で「土ふるい機」を自作しているところです。
構造は単純。 ツーバー材などで木枠を組み、1cm編み目のビニル被覆金網を張ったものが「ふるい」の本体。
土石の重さで金網がずれないように、金網を木材で挟んでしっかり固定する構造です。
これの四方に、土が溢れないよう側壁を設け、スムーズに動かせるよう キャスター を取り付けます。
キャスターはもちろん、走行方向が固定している「固定車」
レール代わりになるのがツーバイ材。
ふるい本体から土が真下に落ちるので、落ちた土がレールの上に乗らないような構造になります。

金網の上に残った石を捨てやすくするために、奥側の側壁は簡単に取り外せるようにしました。
石を捨てる際は、奥の壁を取り外して、ふるい本体を傾けて石を落とします。
下部構造はこんな感じで、出来上がり。
実際にふるいにかけてみる

上部構造を乗せて「自作ふるい機」の完成。 落ちた土を角スコップで取り出しやすいよう、地面にコンパネを敷きます。
最初のうちは欲張って一度に大量の土をふるおうとしたんですが、ふるいを動かすのに力が要る割に、土が速く動かないので効率が悪いようです。
土の動きが悪いので、仕方なくこんな道具を作って手で土石をかき回す羽目に・・・
(´~`)
やっぱり欲張ると良くないですね~ (笑)
次からは、土は少しずつ・・・ だいたいスコップで4~5回分くらいずつ入れて振るったんですが、その方が楽で効率良かったです。
土石の量が少ないと、ふるいを動かした際に土石がよく動くので、気持ちよく土が下に落ちてくれるのです。
ふるい分けの動画
床掘りした庭の土を「自作ふるい機」にかける様子を動画で撮りました。↓↓↓
まとめと反省点
今回、大型ふるい機を自作して土石をふるい分けしてみて、重要だと思ったことを書いてみると・・・
- 最も大切なことは、ふるいにかける土を濡らさないこと。
濡らしてしまうと、ふるいにかけてもうまくばらけない 効率が極端に悪くなる。
対策としては、ふるいにかける土を雨を当てないよう、ブルーシートなどで覆う。
- 一度に大量の土をふるおうとすると、ふるいを動かすのに力が要る割に、土が速く動かないので効率が悪い。
土は少しずつ入れて振るった方が楽で効率が良い。
- キャスターが通る「レール」の部分をこまめにチェック。 ここに土がこぼれていると動きが悪くなる。
金網について
金網については、当初は途中で破れるんではないかと耐久性を心配したんですが、実際には大丈夫でした。
今回ふるった土石の量は 約2.7立方メートル、 つまり 2700リットルくらいですが、少なくともこの程度までは金網が破れないということでした。
金網の目のサイズも1㎝で正解だった思います。
目的にもよるだろうけど、芝生の床土作りを目的としていたので、1cm目で丁度良かったです。
反省点や今後の改善点
- 当初は一度に大量に土を入れてやろうという発想で、ふるい機の側壁を無駄に高くしてしまった。 実際にはこんなに高さは必要ない。
- ふるいの目的によって金網を簡単に交換できるような構造なら、なお便利だったと思う。
庭の土の Before After
庭の堅い土をふるいに掛けた結果、こんなに良くなりました。(^^)v
これが、ふるいに掛ける前の土。 石だらけ。 ↓↓

そしてこれが、ふるいに掛けた後のサラサラした土。 ↓↓

良いですね~ (^^)v これに砂と堆肥を混ぜて、芝生作りの床土にしました。
以上、ふるいの自作についてでした。
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。