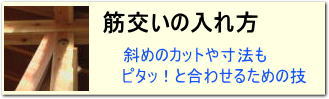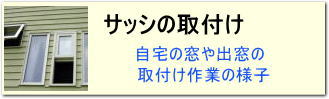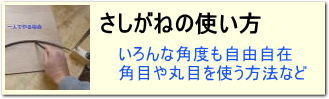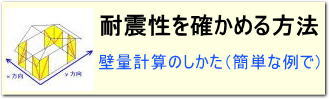壁の下地(筋交い・間柱など)

柱・筋交い・桁と、2倍筋交い金物
自宅セルフビルドの、筋交い・間柱と、透湿防水シート貼り、軒天などの施工の様子です。
ちなみに筋交い(すじかい)は、材木屋さんの世界では、構造材ではなく垂木などと同じ「羽柄材(はがらざい)」に分類されていますが、実は極めて大切な「構造材」です。
筋交いと間柱を取付ける
筋交いの寸法は、現場にぴったり合って、がたつきがないようにしなければならないので、設置した後に乾燥して縮むことがないよう、筋交いに用いる材木だけは、あらかじめ買っておいて、1年ほど乾燥させておいたものを使いました。

寸法を測って墨付けするには、二人以上いる場合は、設置する場所に一人が材を押し当てて、もう一人がそれに墨付けすればいいのですが、一人作業なので、筋交い寸法測定器を自作しました。
「測定器」は、スライドして伸び縮みする本体の両端部に、可動式の正方形の板を取り付けています。
筋交いを設置する場所に測定器を挿入してしっかり伸ばして、クランプで本体を固定します。固定したら、両端部を、正方形の板に着いている蝶ナットで固定し、(これで角度がわかります。)本体中央部の軸に鉛筆でしるしを付けます。(これで長さがわかります。)

「筋交い寸法測定器」の下部
測定器は一旦縮めて取り外し、軸にしるしの付いた位置まで伸ばして、筋交いに用いる材の上に載せ、墨付けをします。
筋交い材は、そうして付けた墨よりも、約4ミリほど長くとって切断するのが経験的にぴったり収まりました。
筋交い材の両端部は、「木殺し」といって玄能でよく叩いてつぶします。そうすることによって、材がもとにもどろうとして膨張するため、多少の縮みがあっても相殺されて、がたつくことがなくなると聞きました。
(確かにそのとおりのようで、設置して数年たってもゆるむことがありません。)

筋交い材は外側から掛矢でたたいてきつめに挿入します。
上下両端部には、2倍筋交い金物といわれる金物を取り付けました。
土台や胴差などの横架材と、柱、筋交いの3つを連結するもので、横架材と柱にそれぞれビス4本、筋交いにはビス5~7本を打つことになっています。
なお、筋交いには、圧縮に抵抗させる圧縮筋交いと、引張りに抵抗させる引張り筋交いがありますが、我が家では全部圧縮筋交い(最近はどこの家も皆そうですが)なので、材の厚さは最低45ミリ、最大105ミリのものを使いました。

筋交いの下部
土台と柱です。手前に見える材は、床の下地になる「大引き」という部材です。
下のほうに使う材は、腐朽やシロアリ防止のためにキシラデコールやクレオソートを塗りました。
なお、圧縮筋交いを入れる場合、基礎のアンカーボルトは、地震などで水平力がかかったときに土台が浮き上がろうとする位置、(即ち筋交いがとりついた場所の反対側近く)に入れることになっています。

ちなみにこれは、引き寄せ金物というものです。
通し柱の両側から胴差しがとりついていますが、地震などで胴差しが通し柱から離れて脱落しないよう、両方の胴差しをお互いに引っ張るようにしている金物です。通し柱には、ボルトを通す穴を開けておきます。
通し柱と、胴差しや台輪の接合部は「傾ぎ大入れ」という仕口です。
通し柱と1階の管柱(くだばしら)は4寸角(12cm)ですが、なるべく欠きこみの少ない仕口を用います。

柱と柱の間には、壁の下地として間柱(まばしら)を455ミリ(1尺5寸)間隔で入れていきます。
間柱は30×105ミリの杉材を使い、上下両端部はホゾ加工して土台と胴差しにはめ込みます。
まず、上の胴差しにホゾを差し込んで、斜めにたて、間柱を湾曲させながら中央部を引っ張って、下のホゾを土台に差し込みます。
このため、下のホゾは経験上、長さ15ミリ程度がいいようでした。
筋交いと間柱は競合するので、構造材である筋交いは欠きこまず、下地材である間柱を欠きこみます。
間柱を建て込んだ後に、寸法どおりに切断加工しておいた筋交い材を、入れる位置にあてて、間柱にあたる位置にマーキングして、丸鋸やノミで間柱を欠きこみます。
この際、間柱材が反れていると正しくマーキングできないので、間柱と間柱の間に、計算上の間隔になるようバカ棒を挟み込み、どの間柱も垂直にたっているようにしてから行いました。

90ミリの太筋交いをクロスに入れているところです。
交差部分は、一方の筋交いを切断して用います。
透湿防水シート・胴縁・軒天

タイベックという名の透湿防水シート張りつけ前の状態です。
窓サッシを入れ終えたら、透湿防水シートをタッカーで張っていきます。シートは幅1mでロール状になっています。
家の下方から順に張っていき、上下の透湿防水シートを10cmほど重ね合わせます。また、コーナー部分などは2重に張って、防水効果を高めます。
透湿防水シートの上から胴縁という18×45ミリの杉材を、柱や間柱にあたる位置に釘打ちして取り付けました。
胴縁は、外壁材の下地になるほか、透湿防水シートと外壁材の間に18ミリの隙間をつくり、空気が循環する通路を確保する効果があります。これを「通気工法」と呼び、最近はどこの家でもこの工法を使っているようです。
空気の通り道を確保するため、胴縁は窓の下部にぴったりとくっつけないで、4cmほど隙間を開けています。

足場をたてられない屋根の上には、傾斜地に合わせた台をつくって、その上に乗って作業しました。
台の下は、滑らないようにゴムバンドを巻いてあります。
なお、サッシ周りにはゴム系の両面テープを張って、その上に透湿防水シートを貼り付けます。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。