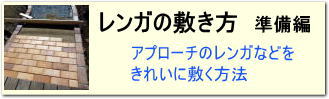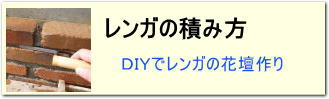レンガ敷きの経年変化
DIYでのレンガ敷きは自分でも納得の出来栄えで大満足でした。
でも完成直後は立派に見えても、年月の経過とともに目地から草が生えてくるとか、レンガ表面が苔むしてくる可能性もあるし、レンガの表面が凸凹してくるかもしれないですね。
特に冬の寒さによる凍上が、この地域では問題なのです。
そこで、経年変化の観察結果を、随時書いていこうと思います。
一冬越えたらこうなっていた(レンガの凍上について)
1 アプローチのレンガ敷き

アプローチレンガ敷きの施工後、一冬越えた3月1日の状態です。
一見、何も変化がないように見えますが・・・

歩いてみると、なんだか違和感を感じました。 よく見ると、ところどころに凸凹が見られます。

アップで見るとこんな感じ
冬の間はほとんど歩いていないので、これは重さによる沈下では絶対なくて、冬の寒さによる凍上と考えます。
うーん、ちゃんとやったつもりでも凍上しちゃったか、ちょっとガッカリ (´~`)
この冬は、最低気温がマイナス15度くらいで、比較的寒い日が多かったです。
4月になってすっかり暖かくなったら、最初にレンガを転圧したこの方法で、再度転圧して平らに戻そうと考えていました。
ところが・・・

なんと!
暖かくなったら、レンガは元の真っ平な状態に自然に戻っていました。
再度転圧する必要なし!!
歩いた感じもしっかり固く締まっていて、全然不安定なところはないです。 これなら安心 (^^)v
2 敷地東側のレンガ敷き

こちら側は、一冬越えても凍上らしき凸凹は全く見られず、施工直後のように真っ平で固く締まった状態でした。
 どうしてアプローチ側と違う結果になったのか、考察
どうしてアプローチ側と違う結果になったのか、考察
理由その1 敷地東側のレンガ敷きは、冬の間全く利用されることはなく雪捨て場になっていて、常に雪に覆われていた。
そのため、雪で保温された状態であり、凍上が起きにくかった。
理由その2 敷地東側は、ほとんどが凍結深度より深いところまで砕石で置き換えてあるので、もともと凍上しにくいと考える。
理由その3 それに比べてアプローチ側は、冬でも毎日雪を払って掃除していたので、レンガ敷きが直接寒い外気に接した状態だった。 だから寒さをまともに受ける。
理由その4 アプローチの場所はよく締まった切土地盤だったため、これを生かし、凍結深度まで砕石で置き換えてはいない。 土は砕石より凍上被害を受けやすいので、凸凹が生じたと考える。
・・・といったところかな。
不思議な現象 なんでこうなるの?

12月のある日、ふと見るとアプローチレンガがこんな状態になっていました。
少し降雪があり、その後ほとんど融けたんですが、特定のレンガの上にだけ雪が残っているのです。

さらに1月になって雪が多くなると、こんな状態に・・ (;゜д゜)

アップで見るとこういう感じ
まさに特定のレンガの上にだけ雪が融けずに残っているのです。
 この現象はいったい何故か? 考えられることは・・・
この現象はいったい何故か? 考えられることは・・・
アプローチには、色の違いで『ゴールド』と『タン』の2種類のレンガ(リージェンシー)を使っていますが、雪が残る・残らないと色の違いとは、関係ないようです。
12月の写真と1月の写真を比べてみると、雪が融けないレンガの配置パターンは同じでした。つまり、まさに特定のレンガだけが融けないのです。
雪が融けないで残るというのは、それだけ地中からの熱が伝わりにくい ⇒ つまり熱伝導率が低いということでしょうから、レンガによって、見た目は同じでもそういう違いがあるんじゃないか?
レンガの材料となる粘土や砂の採取地が違うのか、あるいは焼く前の乾燥状態とか、焼くときの温度や時間とか、判らないけどそういういろんな要素が重なって、製品の熱伝導率に大きな差が出来ているのかな?
まあ、私が考えられるのはこんな程度です。 でも面白い現象ですね。見るのが楽しいです。(^^)
こんな記事も読まれています

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。