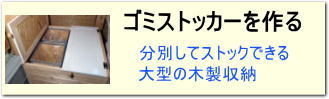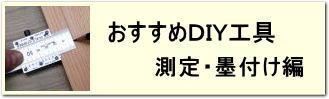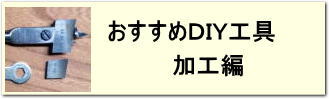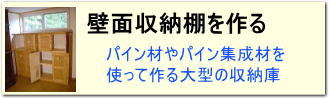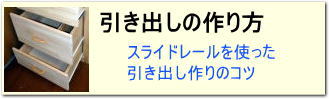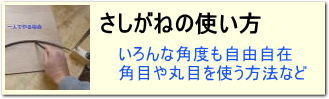カラーボックスを利用して
引き出し式の収納ベンチを作る


収納ベンチといえば、座面を跳ね上げる方式のものが圧倒的に多いようですが、これだと、座面の上に物を置いていた場合いちいちそれらを片付けないと収納物を取り出せない・・・という不便さがありますね。
今回自作した収納ベンチは、本体と収納部分が別々になっていて、収納部分の底にキャスターをつけているため、座面に物が置いてあっても、収納部分を引き出しのように使って収納物を取り出せます。
自作ではありますが、手間と費用を節約するため、内部に市販のカラーボックスを利用しています。
作りもごく単純なため、安く、短期間で作ることができました。
製作過程
本体の製作途中の様子
天板(=座面)は厚さ18ミリのラジアタパイン集成材にステインとニスで塗装したもの。
主に人が座ることを想定するなら、座面厚さは25ミリ以上ほしいと思いますが、今回のは座るというより物を置くことが多い想定なので、18ミリで良しとしています。(人が一人、ちょっと座るくらいなら十分)
側面は、羽目板と集成材で「かまち組み」に作ったパネルです。
本体を上下ひっくり返して見た様子。
背面板はただのベニヤ板です。家の壁側になるため普段は見えません。
天板と、側面パネル、背面板、それぞれは桟木を通じてビスで固定さてれいます。一番簡単な方法かな・・・
収納部分は、羽目板と集成材で作った正面パネルに、市販の3段カラーボックスをくっつけたもの。
底にキャスターをつけ、正面パネルには出し入れのための「取っ手」がついています。
ずずずっ! と奥に押していくと・・・
こんな風に収まります。
普段、座面の上にゴチャゴチャと物が置いてあっても、関係なく収納部分を出し入れできるのです。(^^)v
収納部分の底面を見たところです。
底面は、カラーボックスの背面に相当するので、そのままでは薄ベニヤなので強度不足。
1×4材を3本と、薄ベニヤの間の隙間調整材をはさみ、強度不足を解消しています。
1×4材の両端4か所に、キャスターを取り付けました。
かまち組みパネル作り
パネルの「かまち枠」は、厚さ18ミリのラジアタパイン集成材を使用
木端に、鏡板を入れるための溝を加工します。溝加工はトリマー使用。
かまち枠どおしの接合はビスケットジョイントで行います。
ビスケット加工と溝加工を終えた、側面パネルの「かまち枠」
こんな風に「かまち枠」どおしを組んで・・・
溝の中に鏡板を入れまていきます。
今回の鏡板にしたのは、ホワイトウッド羽目板です。
「かまち枠」を組み、ポニークランプで圧締
※ 画像は、側面パネルを2枚同時に圧締しています。
正面パネルも、基本的には同じように製作

部屋の内装壁がホワイトウッドの羽目板を多用しているため、収納ベンチも同じ羽目板を使うことで、部屋に馴染むようになりました。
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。