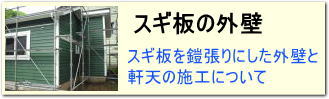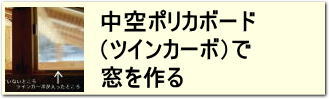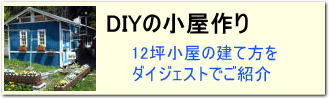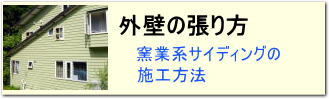外壁スギ板張り
下地の透湿防水シートから仕上げの板張りまで
木造小屋建設のうち、杉板で外壁を作る工程です。
柱や間柱が露出した状態から、まずは透湿防水シートを全面的に貼り付け、その上から杉板をよろい張りにします。
透湿防水シートと杉板(=外壁材)の間に「通気胴縁」を挟む工法が住宅では一般的ですが、この建物は軒天も省略した小屋でもあるため、通気胴縁を省いた簡易な方法で作っています。
透湿防水シートを貼る
この手作り小屋は、小屋といえども壁には防音を兼ねて断熱材を入れる予定だし、外壁が通気性たっぷりのスギ下見板張りなので、なんらかの防水シートは絶対必要です。
それで、家作りにも使われる透湿防水シートを貼ることにします。
透湿防水シートとは
透湿防水シートとは、水は通さないけど、湿気(水蒸気)は通すという性質を持ったシートです。
木造建物の外壁面からの水の侵入を防ぐとともに、壁体内に籠った湿気を外に逃がすことができるので、ほとんどの住宅ではこのシートが使われています。
特にグラスウールなどの断熱材はいったん水分を含むと抜けにくいので、透湿防水シートとの併用は必須といってもいいでしょう。

これが透湿防水シート
50m巻きで3980円でした。 巾は1mです。 有名なデュポン社のものではないですが・・・
もちろん通気性アリです。
タッカーと両面テープで貼り付ける

貼ってま~す。
50m巻きだと軽くていいです。以前、自宅を作ったときは100m巻きだったので、持っているのが重くて大変でした。


タッカーでの固定 両面テープ貼り
窓などの開口部回りには、シートを隙間なく固定するために先に両面テープを貼っておき、透湿防水シートをそこに貼り付けます。

屋外で防水シートなどの接着に適したのが、ブチルゴム系の建築用防水両面テープ。 色は黒いです。
これもホームセンターで購入。30ミリ巾で10m巻きで714円。 厚さが1ミリもあります。
さすがに粘着力は強いですが、キシラデコールなどの防腐塗料を塗った木材面にはくっつきません。

窓回りにグルリと一周、前述の両面テープを貼ってから、次の透湿防水シートが貼られる高さまで、上紙を剥がして・・・
ちなみに、全部の上紙をいっきに剥がしてしまうと、余計なところに誤ってシートがくっついてしまうことがあり、そうなると剥がすのが大変ナノダ (^_^;
必要なところを少しずつ剥がしたほうが無難です。

取りあえず透湿防水シートをダーッと貼ってしまい、窓の部分をカッターナイフでカット。
シートはテープにぴったり張り付いているので、きれいに施工できます。


さて、この小屋の軸組みは、梁の先端が外壁の面より少し飛び出しているので、ここにシートを貼るために、まずは飛び出た梁の周囲に両面テープを貼り・・・


余分なシートを、入り隅に添ってカッターナイフでカット。
これで隙間なくシートが貼れます。
妻壁の処理

同じように、妻壁上部の三角形の部分。
ここは母屋(モヤ)が飛び出ているので、母屋の周囲に両面テープを貼るんですが、貼るための下地がありません。
そこで、適当な角材を、下地として小屋束の両側に打ちつけました。
また、最上部の下地となるはずのタルキは厚さ45ミリのため、厚さ105ミリの小屋束の外面から、(105-45)÷2=30ミリ引っ込んでいます。
だからタルキの側面に、厚さ30ミリの角材を打ち付けて、外壁下地面を揃えます。

ここに透湿防水シートを貼ると、こうなり・・・

外壁としてスギ板を貼ると、妻壁はこのようになります。
こちらは小屋の北側です。

じつは透湿防水シートが1巻きの50mでは、この小屋の必要量に足りません。
でももう1巻き50mを買うのも、余計に余ってしまってもったいないので、西側の下段には、ちょうど余っていたアスファルトフェルトを貼る事にしました。
アスファルトフェルトは透湿防水シートより安いけれど、通気性がありません。1段くらいなら問題ないでしょう(^^ゞ
外壁にスギ板を貼る


材料は森林組合の製材所から購入したスギ板。 厚さ12ミリ、巾180ミリ、長さ4mです。
安いんですよ~ 安すぎて、単価はヒミツです(^_^)
よろい張りにするので、1番下にスペーサーとなる板を取り付け。 ここは腐りやすいので、しっかり防腐剤を塗っておきます。


上下のスギ板は3センチ重ね、重ねた位置の少し上から、ステンレス釘で固定。
コーナー部分はL字に組んだ板をかぶせて小口を隠します。
スギ板の表面は、製材しただけでカンナのかかっていないガサガサ状態のほうが塗料がよく浸みこんで良い・・・という人もいますが、ガサガサ面に塗料を塗るには、塗料がたくさん必要で、触った感じもよくありません。
手間がかかるけど、私は全部のスギ板の片面にカンナをかけました。随分きれいになりました。

上の方を張るため、手持ちの単管パイプで簡単な足場を・・・
コンパネの端材を上に並べて、なまし鉄線で固定。足場の巾は40センチ以上欲しいです。

コーナーや開口部まわりは、白ペンキで塗装してアクセントにしました。
なお、スギ板による外壁張りの手順などは、こちらのページでより詳しく解説していますのでご参考にどうぞ↓↓
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。