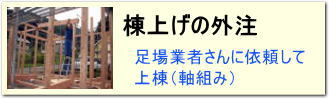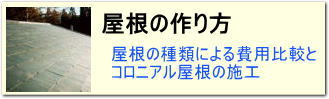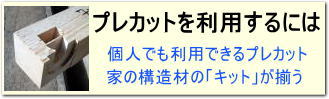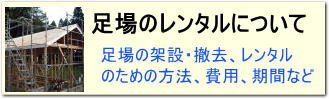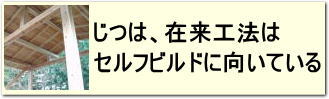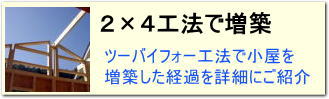棟上げ(木造軸組み)

人にも天気にも恵まれ、
とても充実した気分を味わえました
我が家は木造軸組み工法、いわゆる在来工法です。
木造軸組み工法で家を建てるという工程の中では、建て方作業(軸組みを組むこと)が一番派手なハイライトだと思います。
私はほぞやほぞ穴などの仕口や継ぎ手を、プレカットに頼まず、自分で刻みをしたので、とりわけ感慨深いものでした。
たくさん人手を頼んでおいて、土台据付けから梁・桁を上げるまで一気にやってしまいます。

土台の部材を、基礎コンクリートの上に並べます。
雨降りで、グチャグチャどろどろの日でした。

ほぞの先端に、鋸で、クサビを打ち込むための溝を切り込みます。
運搬途中で破損するのを防ぐため、現場に着いてから切り込むのです。
この後、アンカーボルトの位置を合わせて、ドリルで穴をあけます。

隠れてしまう土台の裏面に、今のうちに防腐剤のクレオソートを塗りました。
雨だったので、この後、すぐに止めました。
翌日、晴れた日にやりなおし。

床下の換気を良くするため、基礎と土台の間にパッキンを挟みこみました。
市販のパッキンもありますが価格が高いので、土木工事などに使われている「プラスチックライナープレート」の厚さ10ミリのものをパッキンとして使いました。
パッキンは一定間隔で並べていきますが、柱の下、アンカーボルトの両側、継ぎ手の下には必ず入れます。
※ ちなみに現在では、住宅専用の基礎パッキンがネットでも随分安く手に入るようになりました。
土台据え付け後、建て方開始
専門家を頼んだほか、知人友人がたくさん助っ人に来てくれました。
横架材のほぞ穴をを柱のほぞに差し込み、逆さ掛矢といわれる道具で下から引っ張って、叩きいれます。
思い切り力を入れて振り下ろさないとダメです。

梁をかけているところ。着々と組みあがっていきます。

角の通し柱に下げ振りをぶら下げて垂直を見ます。
仮筋交いの一端を釘1本留めしておいて、ロープを引いて微調整し、完全に垂直を出してから仮筋交いのもう一方の端を釘で固定します。
羽子板ボルトなどの建築金物をどんどん取り付けて、固めていきます。
何ヶ月もかけて刻みを入れた材料が、きちんと組みあがっていくのは、とても嬉しいものです。 V(^0^)

助っ人が去って、再び一人の作業が続きます。
垂木(タルキ)の取り付けをしています。

家の軸組みがほぼできてきました。
左端、1階の上にかかんでいるのが私です。

屋根下地となる野地板を下から張り上げていきます。
屋根の上に簡単に登れるように、2階からスロープをつたっていけばいいような構造にしていました。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。