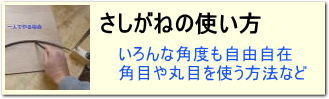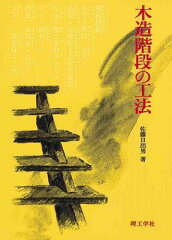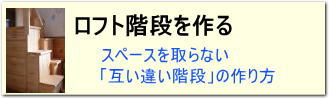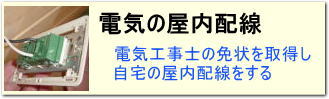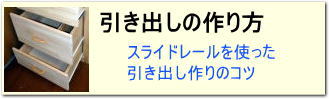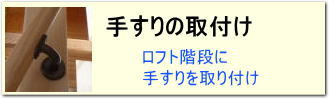家の階段を作る 作りやすい「ささら桁階段」


セルフビルドした自宅は2階建てですので、階段が必要でした。
私の自作階段について、製作過程や設計方法などをご紹介します。
階段を作るのは、家作りの中でも技術的に難しい部類になりますが、その中でも「ささら桁階段」は比較的簡単で、素人でも失敗しにくいと思います。
自作階段のご紹介
階段はただ単に2階へ上るための通路ではなく、家の中の面白空間のひとつだと私は思っています。
2階にリビングを持ってきたので、階段の使用頻度がとても多いということになったのです。
日常頻繁に使う場所だから、普通の家にあるような急勾配の直階段ではなく、一段の踏み面(水平面)が27cm、蹴上げ(垂直高さ)が19cmと、最も歩きやすい緩めの勾配とし、且つ危険が少ないように、中間に踊り場を設けて折り返すように設計しました。
踊り場があることによって、上から下を見たときの恐怖感が薄れ、万一転げ落ちても、直階段よりは怪我が軽くなるはずです。
毎日通る階段であることから、途中両側の間仕切り壁を利用して下の写真のように小物収納の飾り棚を5個つくりました。
私は勝手に階段ギャラリーと呼んでいます (^^ゞ




階段の設計
木造階段の種類には、箱階段、側桁階段、ささら桁階段・・・といったものがありますが、私が勉強した限りではどれも素人には加工が難しそうです。(汗)
その中でも ささら桁階段 が、一番手間が少なくできそうに思えたので、迷わずこれを採用することにしました。(^^ゞ
とはいえ、 階段の設計はむずかしく、何度も座標計算を行い、図面を書き直しては考えました。
最も大工さん気分が味わえる工程です。
ささら桁階段の設計例
わかりやすい数値でイラストを描いてみます。(わが家の実際の階段とは少し数値が違います。)
まず1~2階床面の高低差を均等割りします。
階段1段の高さはどの段も同じにするため、1~2階床面の高低差を13とか14などの整数で割った値に設定することになります。
イラストのように例えば1階床面から2階床面まで2800ミリなら、階段1段の高さを200ミリにすれば、2800÷200=14 で、丁度14段で割り切れる。200ミリなら歩きやすいはずです。
水平面については、階段1段の水平面の長さ(250ミリ)に段数を掛ければ水平方向の必要な長さが分かるという わけです。
あとは家の内部のスペースを見ながら調整。 この例では折り返し階段なので、中間に設ける『踊り場』をどのくらいスペースを取るか検討しながらやっていきます。
ささら桁を受ける梁の高さや位置を決めるには、このような図を方眼紙やCADを使って描いてみれば検討しやすいです。
基準となるライン(基準線)を決め、それを Y=aX+b のような一次式で表し、2本の基準線を連立方程式にして解けば、交点の座標が分かります。
まず座標を決め、次にささら桁との取り合いの仕口の詳細図を描いて検討すればいいでしょう。
階段の製作過程
1、下地の受け梁などを加工・取付け


階段製作の材料搬入
メインの材料となるささら桁の松材と踏み板は、ここにはありません。後で搬入しました。
まず、踊り場の水平面をつくるための軸組みを行うため、部材に刻みを入れます。


掛矢で叩いて、ホゾを差込み。
下げ振りを用いて位置のチェック
右画像の奥に見えるのは、踊り場をささえる柱のひとつ。
当初の設計がいいかげんで(と言うよりも、家をつくりながらたくさん設計を変更しているため)、後で独立基礎コンクリートを打ち足しています。


「平ホゾ」と「蟻継ぎ」で結合させています。
これで、踊り場水平面を構成する柱、梁、桁のできあがりで、これが「ささら桁」を受ける梁になります。
次に、上部の「ささら桁」を受ける梁をかける部分の加工をします。
北側の既存の梁が寸法不足なので、強度をアップするために「まくら梁」を抱かせます。
既存の柱に「添え柱」を当て、まくら梁を乗せかけるとともに、まくら梁と既存の梁をボルトで結合して密着させました。


梁を受ける部分に「大入れ蟻がけ」の刻みをいれます。
大入れの欠き取りは、本職の大工さんが使うような『大入れルーター』などの専用工具を持っていないので、ノミを使い、上記イラストのように加工します。
鋸が使える部分はできるだけ鋸を使った方が効率良し。
さらに、梁の端部の加工


(左の画像は上下逆に置いています。)
上部ささら桁が乗る梁を、設置します。
2、ささら桁の加工・取付け


階段本体の加工に取り掛かります。
「ささら桁」の部材は、厚さ6cmの無垢の松材を使いました。
基準線を墨打ちし、さしがねをあててステップ部分の墨付けをします。
さしがねと基準線の交点から、さしがねのコーナーまでの距離A、Bが、それぞれ蹴上げ(垂直高さ)、踏み面(水平距離)となります。


ささら桁のできあがり。 上部は6段、下部は8段としました。
ささら桁階段は比較的明るく開放的な空間になる一方、桁そのものがすべて見えることになるため、デザイン的要素も重要になります。
この後、桁材にサンダーをかけてつるつるに磨きました。
右の画像は桁の上端部の加工です。(蟻仕掛け)
梁に施した蟻ホゾ穴に落とし込み、羽子板ボルトで緊結することになります。

上下梁間の実際の距離を測り、ささら桁の、計算上求めた線で墨付けしたものを微調整します。
ひとりの作業なので、適当な角材を掛け渡して2階に登り、材に印をつけてからその距離を測るというやりかたです。
この距離測定を間違えると水の泡になるのです。

ささら桁端部の、梁への落としこみ。
ささら桁が斜めにかかる部材であることから、一方だけを上から叩き続けても入りません。
下端を2、3度叩いては2階に登り、上端を2、3度叩いては1階に戻り・・・ということを何度も繰り返して、最後にはきっちりとはまりました。


ささら桁の取り付け風景
仮設足場に左足、踊り場の梁に右足を乗せて、両手でささら桁を持ち上げ、両端の仕口に落とこみます。

下部ささら桁の下端の様子
受け梁の左端が、土台ではなく大引きになってしまったため、補強のために束を1本立てました。これで強度はバッチリ。
なお、受け梁とささら桁は、羽子板ボルトでしっかりと引き寄せ、固定します。(受け梁には、あらかじめ羽子板ボルトが通る穴をあけておく。)


階段室を真横から見るとこういう感じ。
最後に、ささら桁の周囲に床断熱材をはめ込みます。
なお、写真左端に見える穴は、床下点検口用です。
手すりを受ける「親柱」という柱を先に取り付けるのを忘れていたため、この断熱材はこの後とりはずし、再度やりなおす羽目になりました。
(^^ゞ
踏み板を乗せてとりあえず一段落
踏み板は階段室の内装が終わってから正式にささら桁と緊結するので、取りあえず乗せているだけです。
作業のため頻繁に歩くので、踏み板のカンナがけや手すりの取り付けも後まわしです。
踏み板は、少々値は張りましたが、青森ヒバの無垢の厚板を使いました。
階段を通るたびにほのかにヒバの香りがしていい気分です。
この階段は踊り場があるため、あまり恐怖感はありません。
勾配もやや緩めでちょうど良く、思い通りに仕上がりました。
このあと、踏み板を固定し、ツーバイ材を使って手摺を自作しました。
3 踏み板と手摺りの取付け
この階段の踏み板の取付けはとても簡単です。
ささら桁の上に乗せて固定するだけ。
とはいっても、板の乾燥収縮に伴う「反り」や、加工誤差などから、左右の接触面がピッタリ隙間なく・・・というのは至難の業。
そこで、そうした誤差を吸収して板のガタツキを無くすよう、踏み板とささら桁の間に厚さ1ミリほどのゴムを挟みました。

そして、裏からL型金物で踏み板とささら桁を固定してしまいます。
ビスを打つと踏み板がギュッと引き寄せられるため、ゴムマットが圧縮され、ほど良いクッションの役目を果たし、ガタツキもなく快適に歩くことができました。
ちなみにこの方式だと、踏み板はビスを抜くだけで簡単に取り外せるので、例えば踏み板の表面が荒れてきたから鉋掛けをするなどのメンテナンスをする際、とっても便利です。
わが家では猫を3匹飼っていて、彼らのおかげでキズやらシミやらが付きやすいのですが、一度踏み板を全部取り外して鉋掛けしたことがありました。
(その際は、人が生活しているわけなので、もちろん1枚づつ取り外します。メンテしている間はダミーの板を代わりに置いておくというやり方)

左右2枚のささら桁は比較的背の高い材なので、左右に振れる(揺れる)おそれがあります。
それを防ぐため、1か所、全ネジボルトと角座金を用いて、画像のような『振れ止め』を設置しました。
この全ネジボルトの一方の先端は、家の構造材である柱に固定しています。

手摺りは、たぶんこれが一番安上がりかな(^^ゞ
ホームセンターで売られているツーバイ材の中から、かなり吟味して節の無いものを2本選んできました。
これに鉋掛けとトリマーでの面取り、サンダー掛けをし、階段の親柱に固定しただけ。
すごくシンプルで飾りっ気無し。
でも手摺り材としてよく市販されているφ35のタモの棒よりも、断面が大きいので体重をかけてもビクともせず、安心感はあります。

こうなりました(^^)v
ちなみに階段作りの参考にしたのは以下の本です。 階段作りに特化した本って意外に少ないんですよね。
本格的に階段を作ろうと考えている人にはおおいに役立つことでしょう。
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。