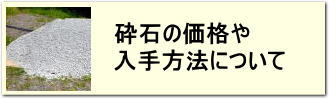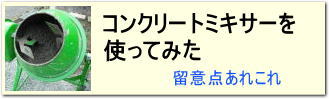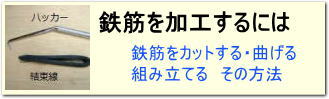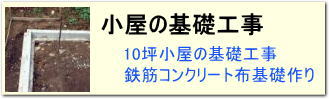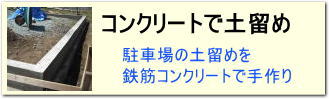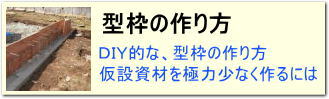生コンの「配合」って何?

生コン会社に電話して生コンを注文すると、「配合はどうします?」 と聞かれるはずです。
そういうとき慌てないよう、生コンの配合の意味を覚えておきましょう。
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。
元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)
第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。
生コンを買うときの「配合」の意味とは
コンクリートの量が少しであれば、砂利と砂とセメントを買ってきて、砂利:砂:セメントを6:3:1くらいの割合(注1)でコンパネの上で混ぜこぜにして水を加えれば、
立派なコンクリートが出来るのですが、家の基礎となるとその量は膨大ですから、手練りでは非現実的です。 品質も安定しませんし・・・
そこで、生コン会社から生コンを買うことになりますが、注文すると「配合は?」と聞かれることがあります。
この場合の「配合」とは、砂利:砂:セメントの割合のことではありません。
聞かれて 「4対2対1にしてね!」 なんて答えると、「は~~?」 ということになります (^^ゞ
生コン会社が聞いてくる「配合」とは、
「呼び強度」 「スランプ」 「粗骨材の最大寸法」 のことです。
正式には「呼び方」、または「呼び」ともいいますが、通称「配合」と言われる場合もあるからです。
場合によってはさらに 「水・セメント比」を指定します。
ちょっと面倒な話になりますが、それらの意味というのは・・・
呼び強度 (単位:ニュートン/㎟)
正式には28日経過した後のコンクリートの、予定される圧縮強度です。( 実際は数字以上に強くなることがほとんど)
ダムなどは16程度、鉄筋コンクリートになると最低18で、以降は3ずつ増えていきます。例えば21とか24、あるいはそれ以上になります。
ダムなどの巨大な塊状のものは比較的小さくてOKだし、むしろ強過ぎるとクラックが入ってしまうので、かえってNG。
逆に比較的小さな断面で強度を必要とする鉄筋コンクリート構造物などは、呼び強度が大きくないとまずいわけです。
スランプ (単位:cm)
わかりやすく言えば、生コンの軟らかさということになるでしょうか。
スランプコーンと呼ばれる容器に入れて引き抜いたときに下がる量(cm)で現わします。
なので、数字の大きい方が軟らかくなります。つまり扱いやすくなります。
水やセメントがたくさん入っていればスランプも大きくなります。
(生コンの時に軟らかいからといって、固まったときに軟らかめになるわけではありませんから・・・念のため)
粗骨材の最大寸法 (単位:ミリ)
粗骨材、つまり砕石(or砂利)の最大寸法です。
大きければ強さはありますが、基礎コンクリートのように中に鉄筋が入っていると、大きな砕石は通らないので、鉄筋どおしや型枠との間隔を見て決めることになります。
水セメント比 (単位:%)
セメントに対する水の割合で、水の割合が少なくなると・・・逆に言えばセメントの割合が高くなることでコンクリートの耐久性が高くなります。
水路や堰堤などの、常に水に接する構造物のコンクリートは、耐久性が要求されるので60%以下が使われ、さらに過酷な、海岸の防波堤などでは55%以下になっていきます。
かといって、どんな場合でもセメントはただ多ければ良いというものでもないのです。
一般の住宅の基礎コンクリートでは、水セメント比までは指定しないことが多いようです。私も特に指定しませんでした。生コン会社で最適に配合してくれますから。
2分30秒
↓↓↓
家の基礎工事ときはどうする?
配合の指定
現在の住宅建築工事の仕様の基本となっている「木造住宅工事共通仕様書」では、呼び強度は24、スランプは特記がない場合は18とされています。
コンクリートの配合及び強度等
出典:2023年版 木造住宅工事仕様書
呼び強度及びスランプは、特記による。特記がない場合のスランプは18cmとし、呼び強度は24N/㎟ とする。
住宅金融支援機構
だから、住宅の基礎を打つ場合は、呼び強度、スランプ、粗骨材径を、それぞれ 24-18-25 にしておくのが無難かと思います。
電話で指定するときの呼び方は 「24 の 18 の 25」 と言えば良いです。
- 粗骨材径は、地域によっては25が無いこともあるので、その場合は20にすれば良いです。
- 鉄筋のない構造物なら、粗骨材径は40でOK
- 伝票には、24-18-25N などと記載されてきますが、最後の「N」はセメントの種類のことで、Nは「普通ポルトランドセメント」のこと。
セメントは他には「高炉セメント」もありますが、住宅基礎では普通使いません。
不必要にスランプを高くしない
スランプが高いと生コンは「トロトロ」した感じになり、流動性が良くて扱いやすいんですが、その分、材料が分離しやすい・・・ つまり砕石などの骨材の多い部分と水っぽい部分が均等に混じらずに分かれてしまって、良いコンクリートが出来にくいなどのデメリットもあるのです。
だから、扱いが楽になるからといって不必要にスランプを高くしないようにしましょう。
住宅基礎は鉄筋が入っていて巾も狭いため、流動性の良いスランプ18ですが、普通の土間コンとかならスランプはもっと小さいほうが良いでしょう。
ちなみに私は昔、土木工事の監督をしていたことがあるのですが、土留め構造物などはスランプ8~ です。 普通の無筋構造物なら12とかでもOK.
配合は、例えば長い距離をポンプ圧送しなければならないところでは、滑りを良くするためスランプを高めに取りたくなりますが、そうするとセメント量が多くなり、固まったコンクリートが必要以上に硬くなり、クラック(ひび割れ)が発生しやすくなるなど、それぞれ微妙にバランスがあります。
生コン会社では、使用する砂利(or砕石)のその日の表面水量まで測って、きちんと指定の強度やスランプなどが出るようにコンピュータで計算して配合するので、やっぱり信頼性が高いです。
我々素人が生コンを注文するときは、「住宅の基礎に使うのだけれど・・」 と、きちんと目的を話したほうが良いと思います。
作る構造物の種類によって適した配合があるし、生コン会社はその専門家ですから。
その場合でも、ここに書いた「配合」の意味を知っておいたほうが便利ですよ。(^^)v
自分で練ってコンクリートを作るには
砂利:砂:セメントの、6:3:1くらいという比率は容積比なので、バケツで測って混ぜれば簡単です。
ただし、砂利やセメントはとっても重いので、プラスチックのバケツだと壊れるかも(^^ゞ
小さめの丈夫な容器が無難です。
※ 現代では「砂利」よりも実際には「砕石」を使う場合が多いと思います。
それほど強度は必要ないところは6:3:1、強度が欲しいところは4:2:1を目安にすれば良いかと。
セメントは、ホームセンターでも25kg入りの普通ポルトランドセメントが500円くらいで売られているので、それを使います。

コンパネの上に、最初に砂を蒔き出し、セメントを加えて、スコップなどで混ぜ混ぜしてから砂利を投入し、さらに混ぜたほうが楽。
最初から砂と砂利を入れてしまうと、そこにセメントを入れて十分に混ぜるとなると、重いです(-_-;)

混ぜた山の中央部をスコップで凹ませ、少しずつ水を投入して混ぜます。一気に入れると水が流れてしまうので、少しずつ・・
練り上げたら、スコップの裏で叩いてみて、柔らかさをチェック。
あとは感覚で、『まっ、これくらいでいいか~』 となったら出来上がり (^^ゞ
ミキサーを使えば楽チン!
コンクリートを自分で練って作るのはかなり重労働ですよ。
かといって生コンを手配した場合は、比較的短時間で打設を終えなければならないとか、ある程度の量以上でないと買えないとか、いろいろ制約もあります。
具体的にはミキサー車が生コンプラントを出発してから1時間半以内に、生コンを型枠の中に打設し終えるというのが一般的な目安。
これを個人の少ない人数でやり遂げるのはちょっとハードルが高いですね。
量については、地域にもよりますが最低でも0.25立方メートル(りゅーべ)からというところが多いようです。これはけっこうな量なんですよね。
その点、コンクリートミキサーがあるとマイペースで作業できるし、少量でもOK。
もちろん、肝心の「コンクリートを練る」という重労働からも解放されるので、DIYとしてはメリットも大きいですよ。
コンクリートミキサーを使う場合の注意点などは別途こちらのページにまとめました。↓↓↓

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。