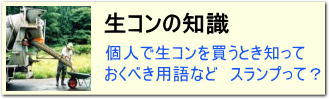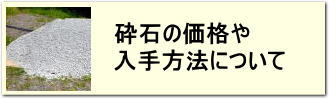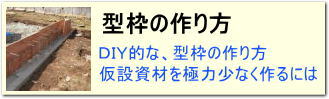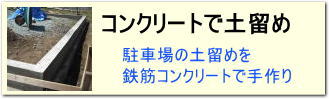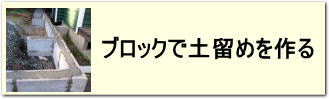コンクリートミキサーの使い方や留意点 生コンとのコストパフォーマンスも比較してみた

外構のDIYに大活躍のミキサー
コンクリートで物を作るには、生コン車を呼ぶのが手っ取り早いけど、条件が合わないと使いにくいですよね。
生コンはある程度の量がないと売ってくれないし、生コン打設は人手が必要なので、マイペースでの一人DIYには不向きです。
個人のDIYでコンクリートやモルタルを扱うなら、市販の電動コンクリートミキサーがあるととても便利です。電動なら扱いも簡単♪
なにしろ、コンクリートを人力で練るのは超重労働なので・・・ まとまった量を人力で練るなんて、とてもやってられません。
私も2010年に約5万円でコンクリートミキサーを買い、いろいろ外構工事をDIYで行ったので、コンクリートミキサー(以下、略してミキサーと呼びます。)を使ってみた結果の留意点や、メリット・デメリットをまとめてみます。
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。
元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)
第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。
ミキサーの使い方と留意点
基本的な使い方
私が購入したのは電動のコンクリートミキサーなので、スイッチを押すとドラムが回る・・・ ただそれだけです。
パワーの点ではエンジン式が勝ると思いますが、扱いやすさの点では電動が超!カンタン (^^)
電源もAC100ボルトなので、家庭用コンセントから電源を取れます。
回転するドラムは、手動でレバーを動かすことによって真上向きから真下向きまで自由に角度を変えられます。
生コンを作るには、回転させているドラムの中に順番に材料を投入し、出来上がった頃に、ドラムを回転させたままレバーを動かして下向きにし、トロ舟やネコ車などに生コンを撒き出すという具合です。
ミキサー本体以外に必要な道具類
ミキサーだけ買っても仕事になりません。さらに以下のものが必要です。

バケツ3個ほど
材料を測って投入するために、摺り切り一杯で10リットルとか、分かりやすいのでバケツは重宝します。私の場合は、① 砂用、② セメント用、③ 出来たモルタルを入れて運ぶ用(モルタル作りの場合)、の3個を使い分けました。
ちなみに砕石は重いので、バケツに入れるのではなくスコップから直接投入です。
左官用の『トロ舟』、またはそれに代わるもの
練り上げた生コンやモルタルを撒き出したときに受けるためのもの。私の場合は古い衣装ケースで代用しました。
ネコ車(一輪車)
撒き出した生コンを『舟』にいったん受けるのではなく、直接受けて運ぶならネコ車が便利散水ホース(ノズル付き)
水を投入するときはバケツよりも断然具合がよろしい。 また、作業後にミキサー内部を洗うときは絶対必要です。スコップ
砕石の投入や、舟に撒き出したモルタルなどを移し替える。角型が使いやすいです。材料の投入順番
ミキサーではなく、左官用舟やコンパネの上でコンクリートを作るときは、普通、最初に砂とセメントを混ぜ、水と砕石は後から入れます。
砕石は重いので、軽くて混ぜやすい砂とセメントを先によく混ぜておいたほうがやり易いからです。
でもミキサーの場合、私の経験では先に砕石を入れたほうが良いようでした。
ミキサーは一日に何度も繰り返し生コンを作るわけですが、その際、前の回に練った生コンクリートの残りがミキサー内壁に付着しているので、先に砂やセメントを入れると、残っている水分によってそれだけが固まってしまいやすい印象でした。
先に砕石を投入すれば、ミキサー内壁を洗う効果があるように思います。
ミキサーは動力で練ってくれるので、砕石が重いなんてことは考えなくてもいいので・・・
ミキサーの傾け角度

ミキサーを回転させながらでも、レバーを使って角度を変えられます。
角度について大雑把にいえばこんな感じ。
投入口が上を向いている
⇒ 材量を入れやすい。攪拌はしにくい。材料があふれ出す心配はない。
投入口が横を向いている
⇒ 材量を入れにくい。攪拌はしやすい。材料があふれ出す心配がある。
投入口がやや上向きの場合
この角度は、バケツを使って砂やセメントを入れやすいです。 この角度のままでも攪拌にはなるけれど、あまり具合がよろしくない。
特にモルタルを作るときは、水を入れると半練り状態の「ベタッ」としたモルタルが、底の方に付着した状態になり、ほとんど攪拌されません。この状態ではミキサーの意味なし。
よく、「ミキサーで練ってみたけど、さっぱり混ざらなかった。」という話を聞くことがあるけど、私の想像では角度に問題があったのかもしれませんね。
投入口がやや横向きの場合

この角度は投入口が上を向いていないので、バケツでの投入はやりにくいけど、攪拌には丁度良いようです。
コンクリートでもモルタルでも、よく混ざってくれます。
材量投入も、スコップで直接入れるならこの角度のほうが具合がよろしい。
でも、これ以上角度を横向きにすると、内容物が多いときは投入口からあふれ出てきてしまいます
やってみて分かったのは、角度を常に一定にするのではなく、作業によってこまめに変えてやるのが良いようですよ。
私の場合は、材料投入時はやや上向き。その後、レバーを使って角度をやや横向きに変えて、よく攪拌させます。
水量の調節
生コンだと、セメントに対する水の比率も厳密に指定することができるけど、個人のDIYでミキサーを使ってコンクリートを作る場合は、計算で水量を求め、測って投入することは現実的じゃないです。
なにしろ、屋外に積んである砕石や砂の山そのものも水分を含んでいるので、雨の日の翌日だと少しの水で生コンが練りあがるし、逆にカラカラ天気が続いた後だと、けっこう水を多く投入しないといけない感じでした。
だから、とても計算で求めることなどできないです。
私の場合は、ミキサーで攪拌しながら散水ノズルで水を少しずつ噴射し、その都度柔らかさ加減を目視で確認しながら、適当なところで止めています。 まあ「テキトー」なわけです。(^^ゞ
気を付けるのは、水を少しずつ噴射して、こまめに確認することです。そうしないと、ついつい水を入れ過ぎてしまうんですよね。
延長コードを使うときは注意!
延長コードを使うと電圧降下が生じて、ミキサーのパワーが落ちてしまいます。
うちの場合も、10mの延長コードを使ったときは何も不便を感じずに使えたのですが、ある日、外電源から遠い場所で作業しようと、延長コードを20mにして使ったところ、事件が起きました。(^^ゞ
運悪く、先に砂とセメントを入れてから砕石を投入していたら、途中で回転が止まっちゃった~!
慌てて電源を切り、仕方ないので半練りの中身をいったん外に撒き出す羽目になりました。失敗!
必ずしも外電源の近くで作業できるとは限らないので、延長コードを長くせざるを得ない場合もあるでしょう。
でもそのときは、ミキサーへの投入量は少量ずつにするのが無難です。
それと、角度を横向きにすればするほど負荷が大きくなるようなので、投入口をやや上向きにして回転させたときに問題なくても、角度を変えた途端にミキサーの回転が止っちゃう・・・なんてこともあり得ます。
後始末の水洗い

作業終了したら、ミキサーの中に付着している生コンやモルタルを洗い落としておかないと固まってしまいます。
これは、ミキサーを回転させながら散水ノズルで直射してやると簡単に落とせます。(ジョーロじゃなく、一番水勢の強い直射で落とす)
ここまでは問題ないんですが、ミキサー使用のデメリットの一つが、後始末の際の周辺の汚れではないでしょうかね。
まず、うまくやらないと周辺に直射の跳ね水が降りかかって汚れます。
内部を洗ったら、投入口を真下にして洗い水を流し出しますが、セメントや砂を含んだ洗い水を地面に落とすことを何度もやっていると、数日後には地面が半分コンクリートのように固くなってしまいます。
これをツルハシで壊して捨てるなんてことも必要になってきます。
だからミキサーを使うのは、ある程度空き地のある、いわゆる田舎ならいいけど、狭い都会の住宅地内で作業をするには厳しいかな~
一日でどのくらいの作業が出来るのか
一人の人間がミキサーを使って一日作業した場合、
どれくらいの量の生コンクリートを作れるのか?
ということですが、私の経験では、下の画像の建物基礎コンクリートを一日で打設したことがあります。

これは屋根付き2階建てウッドデッキの I 字型布基礎なんですが、このときの量は 総延長16.16m 巾 0.15m 高さ 0.4mなので、コンクリートの量が計算上0.9696リューベとなります。 約1リューベ(立方メートル)ですね。
一人だけで砕石・砂・セメント・水を投入し、出来た生コンを型枠に入れて突き固めるという作業をして、一日で楽勝でした。
当然、時間を効率良く使うため、ミキサーが撹拌している間にネコ車で打設し突き固めを行うという工程です。
次の生コンをネコ車に撒きだしたら、すぐには型枠に向かわず、まずはミキサーに材料を投入して撹拌させてから型枠に向かうのです。
なので、このコンクリートミキサーを使えば一人一日で1リューベの生コン打ちが出来る・・・・と考えて良いかと思います。
どちらも一長一短。 いろんな条件を勘案して選べばよいと思いますが、どちらも経験している私からみた双方の長所短所を書いてみますね。
コンクリートの品質
生コンは、きっちりと管理された生コンプラントで、指定された品質(=呼び強度、スランプ、粗骨材最大径、水セメント比など)どおりに正確に作ってくれるし、現場の条件に合わせて最適になるよう混和剤も入れてくれるので、品質に関しては全く問題ないはず。
それに対して、自分でミキサーを使って作る場合は、管理できるのはせいぜい砕石・砂・セメント・水の量の割合くらい。
それも、かなりアバウトな感じにしかならないので、そこそこ使えるコンクリートはできるだろうけど、品質・・・というか、品質の信頼性に関しては生コンに遠く及ばないでしょう。
だから、建物基礎などの重要構造物には生コンを使う方が安心だけど、庭のちょっとした土留めとかに使うコンクリートや、モルタルを練るなどの作業には、ミキサーは十分に使えると思います。
作業性

生コンは何といっても「コンクリートを練る」作業が要らないことがメリットだけど、DIYの立場としては取っつきにくい面があります。
それはつまり、『一定の時間内に打設を終えなければならない』ということ。
生コンの注文は、ほんのわずかな量では受け付けてくれません。地域によっても差異があるようだけど、一般的には最低でも0.25立法メートル(通称「りゅーべ」)です。これってけっこうな量なんですよね。
生コン工場を出てから1時間半以内に、この量を打設しないといけないわけだから(それ以上時間がかかると固まってくる)、一人作業ではとても手が回らず、生コン会社の人に迷惑がかかっちゃう。二人作業ならなんとかできるけどけっこう大変。
だから生コンでの作業は、DIY仲間がたくさんいるとき向き。
そうでない場合はミキサーが重宝します。一人でも十分。マイペースでやれます。
※ ただし、連続した型枠の中に入れる生コンの量が多い場合、つまり、一日で終わらず、翌日まで持ち越してしまうような場合は、やはり友達をかき集めてでも生コンを買って一気に打設するべき。
一人でマイペースだと一日で終わらず、好ましくない『打ち継ぎ目』が出来ちゃいます。 ひとカタマリのコンクリート構造物は、やはりその日のうちに打設して『打ち継ぎ目』はなるべく作らないコト。(巨大な構造物はまた話が違うけどね)
コストパフォーマンス
コンクリートミキサーの購入代金は別として、単純にコンクリートの材料費だけで比較するとどうなるでしょう?
平成23年頃に、私が地元建材店から購入した材料単価をもとに推定してみます。
例として1立法メートルのコンクリートで比べてみると・・・
ミキサーで作る場合の材料費は、セメント:砂:砕石の比率を1:2:4とした場合、
砕石 1立法メートル 4700円
砂 0.5立法メートル 4100円
袋入りセメント 0.25立法メートル 6200円
合計 15000円
これに対して生コンは、地域差があるけれど大体1立法メートル当たり15000円前後
なんと! ミキサー練りと生コンでは、金額的にほとんど同じじゃないですか!
しかも生コンの場合は、信頼できる生コンクリートが、練られた状態で現場まで届けてくれているのに、ミキサー練りの材料費とほぼ同じ金額で購入できる。 生コンって安い!
こうして見ると、コンクリートミキサーは生コン利用と比べて金額的なメリットはほとんど無くて、むしろミキサーの購入費(5万円前後)がかかる分、不利ということになりそう。
しかも購入してしまうと、使用しないときはあの大きな工具をどこかに保管するわけだから、それだけスペースを取られます。
それでも、DIY好きの私としては買って良かったと思っていますよ。
生コン車を手配するほどのサイズでないものを作るときや、自分一人で好きな時に誰にも気兼ねなく、マイペースでコンクリートやモルタルを作れるというのは、大きなメリットだからです。
モルタルを練っている動画
実際に使っているところの動画です。参考までにご覧下さい。
コンクリート作りの動画は撮らないでしまったので、モルタル作りしたときのものです。
↓↓↓
私が購入したミキサーはコレです
購入当時は楽天で5万円ほどでした。|
|
|
|

車輪がついているので、移動は簡単にできます。
車輪2個と、柱1本の計3本で自立するスタイルでした。
車輪は小さいので舗装道なら移動は楽勝だけど、泥濘や凸凹道ではけっこう難儀します。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。







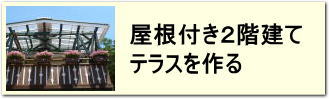
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c5ed779.e14e5df0.1c5ed77a.5fae6ac7/?me_id=1243951&item_id=10000861&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fselect-vita%2Fcabinet%2Fnichiyodaikudiy%2Fimg66945053.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c5ed779.e14e5df0.1c5ed77a.5fae6ac7/?me_id=1243951&item_id=10000861&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fselect-vita%2Fcabinet%2Fnichiyodaikudiy%2Fimg66945053.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)