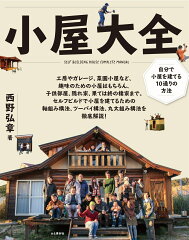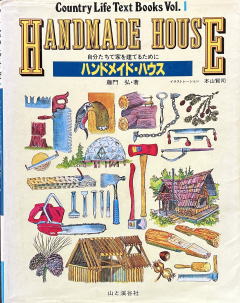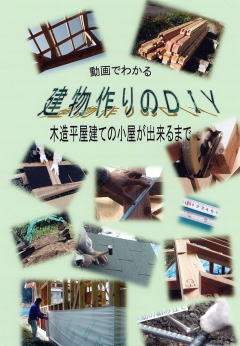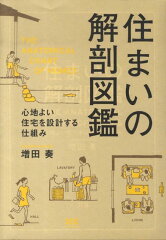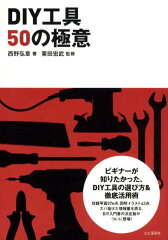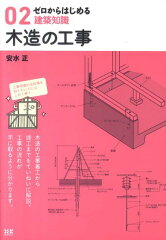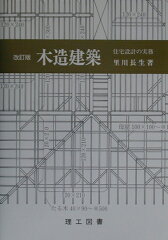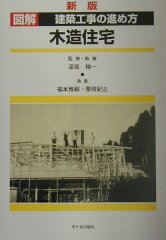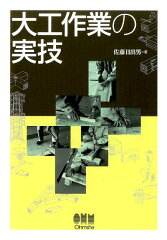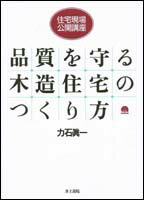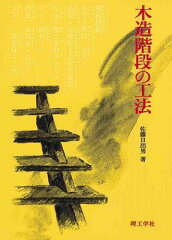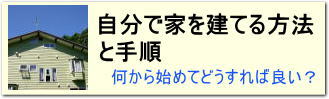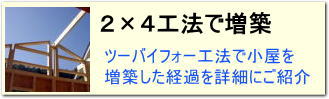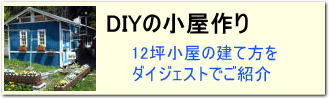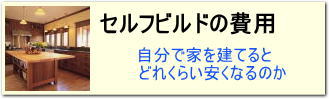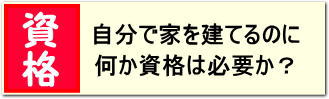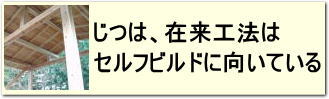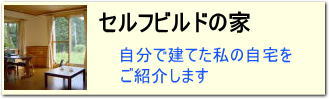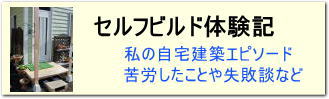自分で家を建てるために役立つ本 セルフビルドの参考書をご紹介
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。
セルフビルド(=自分で家を建てること) をするなら、良質な本による情報収集が欠かせません。
とはいえ、これまで建築関係に縁の無かった人がいきなり専門書を読んでも、ピンとこないばかりか用語すら理解できなくて、苦痛に感じることがありますよね。(^_^;
かくいう私自身は 最初の一冊目に、このページでも紹介する「木造建築ー住宅設計の実務」を読んだのですが、理解できないことはないものの、相当気合いを入れて熟読 しなければなりませんでした。
(汗)
正直、読むのに苦労しました。 すごく役立ちましたけどね。
本というのは出版する際にあらかじめ読者層を想定するわけですが、素人向けに書かれた本と、現場技術者用に書かれた本では当然内容も書き方も違います。
なので私がお勧めするのは、最初は素人向けに書かれた「とっかかり」になる本を読んで全体的なイメージをつかみ、その後に実践的・具体的な専門書を読むという手順です。効率が良いです。
なお、本当にセルフビルドを実行するなら、具体的数値の書かれた実践的な専門書は絶対に必要です。
ここでは、建築に縁のなかった人がセルフビルドに興味を持ったとして、
- まず最初に読んだ方が良い素人向けの本
- ある程度知識がついたところで読むべき、実践のための専門書
に分けて、私がお勧めする本をご紹介します。すべて私が実際に読んでみたものです。
まず最初に読んだ方が良い素人向けの本
素人の読者を想定して書かれたと思われるので、文章も平易ですし理解しやすいです。
これらを読んでワクワク感を高めましょう。(笑)
小屋大全
大きな本でカラーページが多く、見ていてワクワクしてくるだけでなく、実践的なノウハウが満載です。小屋作りの本ですが、数日で作れる小さなものから、自宅にもできそうな大きなものまで、たくさんの実例と細かいノウハウが紹介されており、共通事項として キッチン、トイレ、水道、電気などの設備関係のDIYや、法律知識やライフライン確保など、内容が多岐にわたる、まさに「大全」と呼ぶにふさわしい本です。
事項に紹介する「ハンドメイドハウス」の現代版のようなイメージです。
この本の作者は私の知り合いで、私もこの本の製作にはほんの少しですが協力させていただきました。
小屋(または家)を作りたい方にはバイブルのような存在になることでしょう。多少値は張りますが、それ以上の価値があります。
ハンドメイド・ハウス
何分古い本ですが、ログハウスから2×4工法、在来工法、ドームハウスや組積造まで、さらに共通工事として基礎、床、壁、天井、開口部、左官、塗装、階段、設備工事として給排水、トイレ、電気、階段、風呂のことまで、素人が自分で自宅を設計施工するための知識が、豊富な図解入りで広く紹介されています。
著者独特の説得力ある文体で、グイグイ引き込まれました。
内容が多岐にわたっている分、専門的な深みはありませんので、実践となるとこの本の知識だけでは不足ですが、全般を知るためにも是非とも読んでおきたい一冊です。
私の家づくりの出発点ともなった本です。
これまでにもう5回くらいは繰り返し読んだでしょうか。時には一杯やりながら読み返したり・・・
一種のバイブルのような存在です。
350万円で自分の家をつくる
家といっても、小屋に近いような極めてシンプルな家をモデルにしているので、万人に合うわけではありませんが、わずか6か月で集中して効率よく作っていくその考え方は見事だと思いました。写真は少なく、手書きイラストが中心ですが、著者は建築・設計を生業にされているだけあって建築確認のことや法的なことは詳しく書かれています。
自分でわが家を作る本。
これは「私が読んで参考になった本」ではなくて、「私が書いた本」ですが・・・ (^^ゞ私が参考書を読んで実践してみた経験をもとに、「本当はこういう知識・情報が欲しかったんだ」というものを集めて1冊にまとめたものです。
執筆にあたって留意してことは、① とにかく情報量を多く、② 楽しく分かりやすく、③ 素人が一人で建てるための、建築本には書いていない裏ワザを多く・・ということです。写真やイラストがたくさん入っていますよ。
「自分で家を建てられないかな」と漠然と考えたら一読してみてください。きっと現実味が増して勇気が沸いてくるかも・・・
※ 最初は2006年10月に出版されましたが、翌年12月に出版元の山海堂が倒産し、約1年間書店に無い状態となっていました。 しかし、2008年11月に「山と渓谷社」から再販されました。 新装版は表紙デザインが違いますが、中身は以前とほとんど同じです。 ただし、建築基準法改正に伴い「設計編」の記述が一部変わっています。
動画でわかる建物作りのDIY DVD3枚組
これは書籍ではなく、計3時間30分に及ぶDVDビデオです。
予算60万円で10坪の木造小屋を、基礎から木材加工、床、壁、屋根まで、ほとんど一人で作っていく過程を、映像で詳細に記録し、第三者がよくわかるように解説をつけたものです。(建築費用内訳などの付属資料付き)
このホームページ管理人の私が作りました。(^^ゞ
動画ですので、本を読むよりはるかによく理解でき、極めて具体的な内容ですので、すぐに実践できるはずです。
これまでに1万人ほどの方が購入され、大変好評をいただいております。
住まいの解剖図鑑
設計の中でも、構造的なことというより、「間取り」についての知識を得るために、とても参考になる本です。建築を学ぶ学生向けに書かれたような内容ですが、素人がはじめて自分で家を設計するときにも非常に役立つ内容が豊富だからです。図解が多く、文章も平易で読みやすいです。
住宅のあらゆる部分について、標準的とされるサイズや方向などが「なぜそうなっているのか?」という視点で分かりやすく解説されています。
例えばドアの開き方向とかキッチンや椅子のサイズや高さ、人の動線に必要なスペースなど・・
これを読んでから作った間取りと、読まないで作った間取りでは、家の住み心地に大幅な差が出ることでしょう。
家を建ててから後悔しないためにも、設計の初期段階で是非ご一読を・・・
DIY工具50の極意
工具の使い方について書かれた本の中では一番詳しく解説している本のひとつではないでしょうか。 とにかく写真が多くて、裏技的なことまで紹介しているので情報量はすごく多いです。使い方だけでなく買い方や、こういうのは選ぶと損だといったことまで載っているので、これからDIYをはじめようという方には工具選びの前に是非一読をお勧めしたいものです。
山小舎を造ろうヨ - 少し人生を考え直したい人に
家づくりの実務には直接関係ないですが、隠れ家的な山小屋をつくりたい私などは、大変気に入っている本のひとつです。最低0.5坪の小屋からはじまって、少しずつ大きくしていったときの間取りを紹介していて、最後は6坪の「豪邸」になります。
人間の暮らしに本当に必要な空間や設備とは何だろうと考えさせられる、率直に面白い本です。
ある程度知識がついたところで読むべき、実践のための専門書
木造住宅工事仕様書 フラット35対応 2023年版
住宅金融公庫から融資を受けることのないセルフビルドは、この本に書いてあるとおりに家をつくる必要はないわけですが、耐震性、断熱性など住宅に必要な一定レベルの性能を確保するにはどうしたらいいか、非常に参考になる一冊です。私が自宅建築した後に読んだものが平成15年度改訂版ですが、もっと早く読んでおくべくだったと思いました。プロは当然のように持っているはず。
今では、セルフビルドをするなら必須の一冊でしょう。
仕様書本文は専門用語も多いですが、図解つき解説がついているので良く分かります。
意外に価格も安いですよ。(当時は1,100円でした)
(私が読んだのは15年版ですが、もちろん、最新版を購入されたほうがいいです。)
ゼロからはじめる 木造の工事
極めて実務的な本。基礎から内装まで、家作りの全工程にわたって工事のポイントが解説されていますが、文章と写真と図面のバランスが良く、また、数字(部材の寸法やピッチ・スパン)も具体的にたくさん出てくるので、即、役に立つ内容が多いです。
各種の納まり図、例えば建具回りの断面などがどうなっているか、断熱材と構造部分の取り合いはどうすればいいか・・などが豊富にあるので、木造建築の経験のない素人がセルフビルドをする際には、強力な助っ人になることでしょう。
木造建築-住宅設計の実務
在来工法で家を建てるなら、設計段階で是非とも読んでおきたい超オススメの一冊です。梁や根太のスパン別、ピッチ別標準寸法や、壁量計算のしかたなどが具体的に書かれていて実務的です。
また、2階床の設計は在来工法では一番難しい部類ですが、そこに重点を置かれて説明されているため、よく理解できました。
実務的ですが、素人が読んでも比較的分かりやすい本です。
木造住宅施工の実務手順 - 図解チェックシート175
現場で作業する人の立場にたって、着工準備から基礎、構造体、内外装、設備工事にいたるまで、各工程のフロー図、手順、ポイントを書き記した手引き書。これらが全66のチェックポイントとして取りまとめられており、各ページには要所を示した図解がついています。
これはプロの現場監督者向けに書かれたと思われる実践的な手引き書であり、実際の工事にあたっては非常に役立ちました。施工の順番についてもよく分かります。
工法は、在来工法、2×4工法の両方について記載されています。
図解建築工事の進め方 - 木造住宅
在来工法で家を建てるなら、施工をはじめる前には是非とも読んでおきたい、これまた超オススメの一冊です。基礎工事から構造材の墨付け、刻み、建て方、筋交いや窓枠、間柱~屋根や壁の作り方、施工方法を、豊富な写真(白黒ですが)や図解で分かりやすく詳しく説明しています。
特に、軸組みの設計や墨付け、刻みのことが非常によく理解できます。
施工事例の写真を見ると、基礎工事にしろ刻みにしろ、昨今専門業者が行うような、メタル型枠に生コンポンプ打設、刻みはプレカットというやり方ではなく、一昔前の手加工中心の事例です。
そのためか、Amazonレビューには酷評している方もおられますが、しかし、大型機械や設備をもたない個人のセルフビルドを考えるなら、かえって役に立つ情報でした。
大工作業の実技
教科書みたいな本なので興味がないと読むのはつらいかもしれませんが、在来工法でのセルフビルドを考えている人や、大工作業の技術的知識を覚えたい人にとっては、まさにバイブル、虎の巻のような本です。私のセルフビルドでは自分で墨付け・刻み加工をしましたが、この本が教科書でした。
各種の継手・仕口の墨付け、刻み加工をする際の、具体的寸法や手順についても、詳しく記述されています。
また、大工道具(のみ、かんな、墨壺など)の扱い方の基本から、木のクセについて、木造建物各部の納め方まで幅広く専門的知識を解説しています。
最初に書かれたのは1970年代と古いですが、時代とともに工具は進歩しても、技術の基本は変わっていないと思われるので 、本格的にやるなら是非手元に置いておきたい本になります。
品質を守る木造住宅のつくり方
家作りの全工程を通して、実際の工事現場の写真から、よくある良い例と悪い例を掲載し、施工で気をつけるべきポイントを解説しています。セルフビルドは、いざ工事を始めてみると、こんなときはどうするんだ(?)と悩む場面が多々出てきます。細かい悩みや疑問が本当に多いのです。
この本はそういうことを解決し、正しい施工・良い家作りに導いてくれるありがたい存在です。写真が豊富でとてもわかりやすいです。
工事をはじめる前にぜひご一読を・・・
業者に家作りを依頼する施主の方でも、読んでおくとためになると思います。
建築確認申請マニュアル コンプリート版2022-23
私が読んだのは2007年版ですが、このリンクは2022-23年版にしてあります。建築確認は、延べ床面積が100㎡以内ならば無資格者でも申請できる(現に私は自分で自宅の建築確認申請をしました。)ものの、平成19年の法律改正で、面倒さが増しました。 (´~`)
この本は、最新の法律に添って建築確認の図面を描き、申請するためのノウハウに特化した本で、項目ごとの根拠条文なども頻繁に出てきます。これはおそらく現役の建築士が読むために書かれたであろう内容で、非常に専門的です。
法律の文章が苦手な人にはちょっと面倒かもしれませんが、素人が読んで分からないというわけではなく、建築士資格のない人が自分で建築確認申請をしようとするならば、必須の本といえるでしょう。
二級建築士 はじめの一歩 学科対策テキスト
私たちはべつに二級建築士になろうとしてるわけではないですが、建築士になるための勉強ということは、即ち建築に詳しくなることですから、為になることがたくさん詰まっています。この本は建築士になるための専門的な勉強をはじめる前の入門書なので、素人でも比較的わかりやすい文章で読みやすく、計画から関連法規・構造・施工と、一通りの知識を得ることができます。
もっとも、セルフビルドで木造建物をセルフビルドするだけなら必要ない内容(公共施設やRCなど)も含まれていますが、そういうところは読み飛ばしておけばよいでしょう。私もそうでした。(笑)
この本を読んでおけば、特に法規関係は強くなれます。
木造階段の工法
やや古いですが、さすがに階段について特化した本だけに詳しいです。図面やイラストも豊富にあります。本格的に階段を作ろうと考えている人にはおおいに役立つことでしょう。
私はこの本を参考に自宅の階段を作りましたが、この本にあるような本格的なものではなく、自分のオリジナルを加えて、とても簡単な構造のものにしました。(^^ゞ
世界で一番やさしい建築図面
プロの建築士向けに書かれた本なので非常に専門的。素人のセルフビルドでここまでの知識は必要か?というレベルですが、自分で設計して図面を描くことからはじめるなら、良い教科書になると思います。
伏図を描いていくための手順などが、個人的には参考になりました。
また、設計をプロに頼んだ際に出てくる詳細な図面の見方を覚えるなら、この本があれば心配ないでしょう。
新・木のデザイン図鑑
私が読んだのは旧バージョンの「木のデザイン図鑑」ですが、リンク先は新版のほうです。高い本ですが、それを補って余りあるものすごい情報量! まるで、建築・家具など、木に関する百科事典の様相です。私も、興味ある箇所の拾い読みしかしていません。
中身も濃く、専門的なイラストも豊富で、この本一冊覚えられれば、木のこと、木造建築のこと、木の家具のことについてかなり博識になるでしょう。けっこう大変ですが(笑)
全部読めなくても、手元に一冊置いておけば安心する・・・そんな感じの本です。
木造住宅用接合金物の使い方
軸組み工法に付き物の建築金物について、Zマーク表示金物と、同等の認定金物について、その使い方を解説した本。
個別の金物(商品)ごとに、どこにどのように、どの釘(またはボルト)を何本使うかなど、極めて実務的なことがらを分かりやすいイラストで描かれています。
金物に関してはこれ一冊あれば万全でしょう。
書店にはなく、発行元である㈶日本住宅・木材技術センターのホームページから購入できます。
⇒ こちらから
結局、最初に読むのはどれがいい?
たくさんご紹介しましたが、おそらく・・
こんなにたくさん読んでいられるかよ! いったい何から読んでいけばいいんだい?
と思われたかもしれません。(汗)
時間も費用も限られる中で、本当に厳選して 「これだけは読んでほしい!」という本を選ぶとすれば以下の2冊です。
手前味噌でスミマセン (^^ゞ
でも、私自身がセルフビルドを体験する中で「こういう本が欲しかった」という思いで書きましたので、素人が感じる素朴な疑問には敏感なつもりです。
あと、作るのが家ではなく小屋であれば、
を、お勧めします。 またまた手前味噌でスミマセン (^^ゞ
なお私は2×4工法のことは詳しくありませんので、2×4工法で家をセルフビルドする計画でしたら、上記のほかに2×4工法を詳しく解説した本をご覧下さい。
現在(2024年1月時点)は、私がセルフビルドをはじめた頃(1994年秋)とは全く違い、Youtubeで本職の大工さんや設備屋さんたちが優れた動画をどんどん公開されておられますから、本と合わせて勉強されれば効率よく情報収集できるはずです。 Goog Luck !

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。