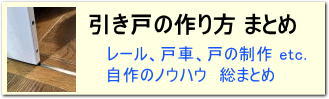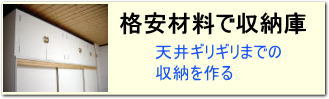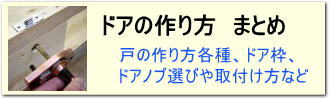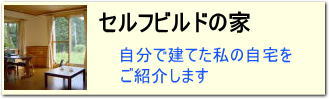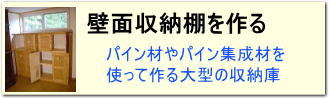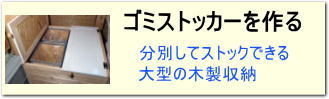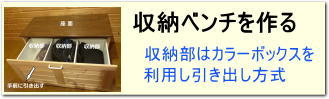たっぷり収納の押入れを自作
布団を横2列に余裕で収納
押入れも自分でつくっちゃおう!

扉と側面には、市販の白い壁紙を貼りました。
取っ手は自作
普通の押入れって、布団を収納するには、なんて中途半端なサイズなんだろう!と常々思っていました。
普通の押入れの内法は1m70cmくらいなので、 布団を2列並べて収納すると狭くて、押し合いへしあい状態となりませんか? 通気も悪いし、カビも生えそう (-_-;)
押入れの両側にある柱の間隔が普通は1間(1.82m)なのでそうなっちゃうんでしょうね。
では自宅に、間口の広い押入れを作ったら? そうすれば自由なサイズで余裕で収納できるし・・・
・・・ということで手作りし、出来上がったのがコレです。
これは普通の押入れと違い、巾が2m20cmあります。布団2列を楽々収納できますよ。(^^)v
この押入れの設計方針
- 布団を2列余裕で収納するために、押入れの巾は2m20cmを確保する。
こうすれば両サイドに余裕ができて、通気も良くなる。
- 中間の棚より上は布団を、棚より下には衣装ケースを収納する。
- 下段は、衣装ケースを3段積める高さを確保する。
- 扉を閉めても通気の良い押入れとする。カビなんか生やしてたまるか!(^o^)┘
ホームセンターから2×4材とシナランバーコア合板を買ってきてDIYで作ったものです。
材料費は3万円くらいです。 丸ノコを持っていれば割と簡単に手作りできますので、製作過程をご紹介します。
手作り押入れの寸法
断面図と正面図はこのようになります。
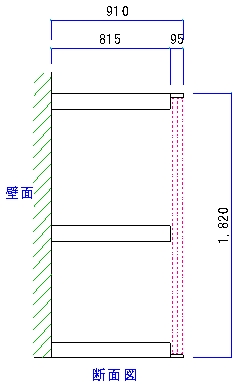
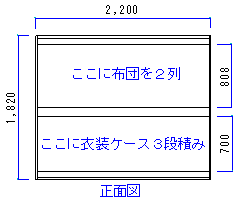
- 布団2列が収納できる押入れは、間口(巾)が2m20cmほど必要です。
- 棚の下は衣装ケースを収納する予定なので、高さを70cm取りました。衣装ケース1個の高さは22.5cmなので3段積むと67.5cmとなり、丁度良いのです。
- 押入れの造作に使う材料は、面部分は厚さ15ミリのシナランバーコア合板、根太等は2×4材を使いました。
- 使う材料に無駄が出ないよう、合板のサイズである 1820 × 910 にあわせて、押入れの断面の大きさを決めました。
- 手前の引き戸のスペースを除けば、棚板の奥行きは 815ミリとなりますが、衣装ケースの奥行きは長いものでも73cmであるため十分。布団もちゃんと収納できますよ(^^)v
棚板の作り方
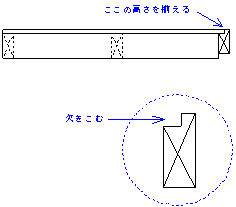
棚板は合板ですが、合板というのは木口(断面の部分)が毛羽立っていたりして内装には向かないので、木口が隠れるように左図のように納めます。
そのためには、棚を支える根太のうち、一番手前の根太を、左図のように合板の厚さ分15ミリだけ欠き込みします。
それは丸ノコを使って次のようにやりました。
押入れ本体を作る


材料を固定して、丸ノコに平行ガイドをつけて上と横の2方向から切り込みを入れます。
切り込み深さは上からは合板の厚さと同じ15ミリ、横からは20ミリです。
棚板を支える一番手前の根太は、あらかじめこのように欠き込みしておきます。
切り取った端材は、押入れの見切り材としても使えるので捨てないで取っておくと何かと便利。
なお、枠材はすべて2×4材を使いました。(単に安いから・・)

枠を壁面にビス(コーススレッド)で固定します。
ビスを打ち込む位置は、間柱など壁の下地のある場所です。
一番下の棚を構成する根太を組んで、枠をつくったところ。
接合はただ単にビスを打っただけです。 手前の根太は15ミリ高い位置に固定します。

一番下の棚にシナランバーコア合板を貼り付け、次に、あらかじめ組んでおいた中段の棚の枠を取り付け。
一人で作業して正確な高さ位置に固定するために、まず700ミリの長さに切った端切れ合板を壁面に2箇所打ち付けておき、その上に枠を乗せ掛けて壁にビス打ちします。
枠の前面が倒れないように、やはり700ミリに切った材料を仮に立てておきます。

押入れの側板として、両端に合板を打ち付け。
そのままでは強度がでないので、中段の棚と下段の棚の間に700ミリの2×4材を咬ませて固定します。

同じようにして上段の棚を固定。
この後、布団収納スペースの壁面に「押入れ収納ボード」という押入れ用の石膏ボードを貼り付けます。
普通の石膏ボードは1枚300円ほどですが、押入れ収納ボードは表面をきれいな紙で仕上げている分、1枚の価格は700円ほどでした。
衣装ケース収納スペースの方は、普通の石膏ボードで十分でしょう(^_^;

棚床と奥の壁、側板との境すべてに見切り材を取り付けて、隙間を塞ぐとともに見栄え良くしましょう。
見切り材はこれまで貯めこんでおいた端材を使いましたが、丸ノコに平行ガイドをつけて切り出すこともできます。

押入れ前面の扉は3枚引き戸にしました。間口が2m20cmもあるため、巾910ミリの合板2枚でも足りないのです。
引き戸をすべらせる敷居と鴨居は、一般的には一枚の木材から溝を切り出してつくるのですが、「ミゾキリ」などの電動工具を持っていないことと材料費節約のため、家にあった厚さ24ミリのパイン集成材をベースにして、その上に小角材を打ち付けて溝をつくることにしました。
写真は、ベースの上に角材を打ちつける位置を印しているところ

まずベースの板を床にビスで打ち付けます。ビスを打つ位置は、小角材が取り付くライン上にするといいです。
あとでビス頭が見えなくなります。
その後、小角材をケーシング釘で固定します。

敷居が固定された状態です。 同じようにして鴨居もつくります。
扉(3枚引き戸)を作る

扉はシナランバーコア合板をただ切っただけですが、底2箇所に戸車をつけます。
戸車は本来、ドリルやノミで穴を開けて埋め込むのですが、合板の厚さは15ミリしかなくて戸車と同じなので、穴をあけるのではなく切り取ることにします。
ジグソーで戸車より一回り大きく円弧を切り取ります。

戸車を取り付けました。

敷居に3枚の引き戸が納まったところ。
15ミリ厚さの引き戸に対して、溝の巾は18ミリです。 きつ過ぎず緩すぎず、丁度良い巾となりました。
戸車がついているので軽く開閉できます。

押入れの側面、上面にはシナランバーコア合板を貼りましたが、木口をカバーするために、プラスチック製の「カブセ」(=被せ)をかぶせます。
丁度15ミリものが市販されています。

取りあえずこういう感じになりました。
扉と扉の間に9ミリの隙間があるので、そこが空気の通り道になることを期待しているんですが・・・
 扉の側面にはシナロールテープを貼りました。
扉の側面にはシナロールテープを貼りました。
シナランバーコア合板の木口を隠す専用の粘着テープですが、材料はシナ合板と全く同じなので、違和感なく仕上がります。

扉表面及び押入れ本体の側面(つまり見える面)には、市販の壁紙(ビニルクロス)を貼りました。
貼るための道具一式も千円足らずでパックされたものを購入。

この壁紙は、裏面を水で濡らして糊上にする再湿壁紙なので、台所用スポンジで水をつけてます。
関連ページ ⇒ 水だけで貼れる壁紙の貼り方

取っ手は、広葉樹のタモの端材から切り出して自作。
オスモオイルのノーマルクリアを塗って仕上げました。 これを扉の裏側からトラスネジで固定。

押入れの出来上がり!
布団が2列、余裕で収納できます。
周囲の壁と同じ色の白にしたため、部屋が明るく感じられるようになりました(^^)
で、これには続編があり、今度は押入れの上、天井までの空間にも収納を作ることにしました。
⇒ 大容量収納ボックス
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。