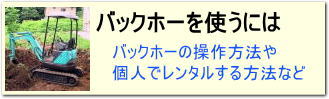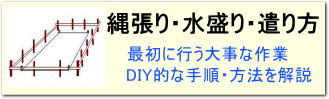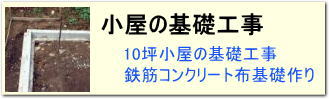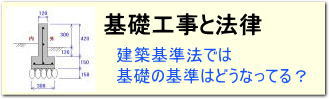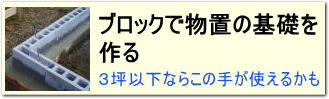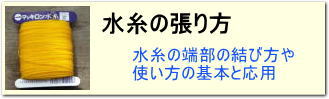凸凹土地を均し、水平をチェックする方法
このページでは、緩やかに傾斜していたり凸凹している荒地を手に入れたとして、自分で家を建てるために最初に直面する「整地」について、一個人でできる現実的な方法について紹介してみます。
土地を平らにする
家を建てるには基礎工事で必要ですが、そのためには、まずは整地です。
建築の本を読むと基礎の作り方が載っていますが、大抵は
敷地はすでに平らに造成されたものでアル・・・との前提 で書かれています。
ところがセルフビルドで家を建てようなんて人は、都会の真ん中のきれいな造成地に建てようという人はごく稀なのでは?
どちらかといえば田舎
それも、ひょっとして住宅地として造成された土地じゃなく原野? 山? (-_-;)
だから基礎工事をはじめるのは、一般的には建物の形を敷地に印す「縄張り」(別名「地縄張り」)からなんだけど、実際のセルフビルドでは「整地」からはじめなくてはならない場面が多いと思います。
敷地が傾斜地だったり凸凹が激しいと、縄張りも遣り方もできたもんじゃない。
ちなみに私がセルフビルドで自宅をつくったときは、多少の凸凹や高低差を無視して強引に遣り方をかけて基礎工事をはじめてしまったために、深いところではかなり深く穴を掘らなければならず、その後何かと大変苦労しました。(反省)
(^^ゞ
整地に伴って残土がたくさん出る
例えばこういう傾斜のついた敷地に建物を建てる場合、どうしましょう?
これは、高い場所から削った土を低い場所に移動させて盛り土し、その上に家を建てるというイラストです。
こ・・これは問題アリですよね。 盛り土したところはいずれ沈むから家が傾いてしまう恐れ有り。
結局、盛り土を避けるなら一番低い高さにあわせて建てることになるかと思います。(左のイラストのように)
ということは、一口に整地といっても、ほとんどは土を掘り取って捨てる作業なわけです。
だから傾斜地を整地すると残土がたくさん出るのです。
1立方メートルの土を掘り出すと、その土の量は膨らんで1.25立法メートルにもなります。
(土の質によってかわるけど、ほとんどの場合は予想外に膨らみます。)
建てる場所がもしも傾斜地だったら、残土を捨てる場所があるかどうか確認したほうがいいですよ。
敷地ギリギリにしか建てられない狭い土地でしかも傾斜地ならば、残土を捨てるところがないため、誰かの土地に捨てさせてもらうか、しかたなく盛り土の上に建てることにして地盤深く杭を打ち込むとかを考えないと・・・
手掘りは大変! 機械を使おう
整地するときは、カッチャやスコップで手掘りするのもいいけど、
かな~~~り!! 大変な作業
になるので腰が壊れるかも (-_-;)
私としては、無理せず機械力を使うことをお勧めします。
ミニバックホーがあると非常に楽!
使用経験がなくとも、単純な動作なら短時間で慣れることが出来るので心配ないです。私も未経験でしたが、すぐに慣れてとても重宝しました。
 建設機械のレンタル屋(リース屋)さんで借りられますが、今はいろいろ厳しくなっていて、運転資格(車両系建設機械運転技能講習終了証など)の確認をするところもあるようです。
建設機械のレンタル屋(リース屋)さんで借りられますが、今はいろいろ厳しくなっていて、運転資格(車両系建設機械運転技能講習終了証など)の確認をするところもあるようです。
資格をとってバックホーで楽に作業するか? 根性で手掘りするか?
いずれにしても、はじめから平らな敷地に建てるのが一番いいですね。
なお、バックホーの資格を取る方法や基本的な操作方法などは、こちらのページにまとめています。↓
掘りながら水平を確認するには
個人のセルフビルドで、特殊な器械を必要としないで正確に水平を見るには水盛り管を使えばいい・・・と良くいわれています。
水盛り管は、水を入れた缶の底近くからホースが伸びていて、ホースの先端付近は透明になっていて水位が見えるようになっているもので、水面の高さはどこでも同じなので、ホースの水位を使って「遣り方」の各杭に水平の印をつけるという方法ですね。
合理的で理にかなった方法だと思います。
水盛り管が使える場所には限りがある
さて、水盛り管を使ったやり方は簡単で正確なんだけど、実際はそれだけでは不便を感じるときがあります。
建てる敷地が、真っ平らにきれいに均された理想的な場所ならいいけれど、傾斜していたり凸凹があったりすると・・・(というか、住宅用に開発された分譲宅地でない限りほとんどそういう場所だと思いますが、)
「遣り方」をかける前にある程度整地しなけりゃナランということになり、整地段階では水盛り管だけでは何かと不便なのです。
さらに敷地内の高低差が大きければ、水盛り管だけでやるのは難しいです。
正攻法はオートレベル
水盛り管だと、杭を打ったり「遣り方」をかけてはじめて水平を見る基準ができますが、杭や遣り方がなくとも、何もない状態の広い範囲で、いつでもどこでも地盤の高さを確認できるようにするには、やはり業者が使うように「レベル」という器械があるといいです。
レベルは「オートレベル」ともいい、これがあると、とーっても便利!
私は大学で測量を習ったし、仕事でも測量を少しやっていたので測量器械を扱えますが、測量器械の中でもオートレベルはトランシットなどと違い、据え付けるのにたいして技術は要りません。
一番簡単なものなので、少し慣れれば誰でも扱えるはずです。
しかし・・・便利なのは分かるけど値段が高い!
通常でも最低3万円以上はするし、三脚も必要です。
(ネットオークションでは5千円なんてのも出品されてましたけど・・・)
8分46秒
↓↓↓
お金がかからない現実的な方法
個人のセルフビルドで、オートレベルを買うだけで3万円も出すのはもったいないと感じますよね。
そこで私が行った一工夫をご紹介します。 お金をかけずに、現実的に整地時の水平のチェックが出来る方法です。

これは私が工房建築のために敷地を整地したときに活躍したのが、自作の簡易レベルです (^^ゞ
日曜大工をする人ならば大抵持っている「水平器」
2千円以内で買えるこのシンプルな測定具を使います。もちろん長い方が(60cm以上)精度が出ます。
簡易レベルの作り方・使い方
コンパネを長手方向に巾10センチくらいに切り、その1m80cmの木端の中央に水平器をビニールテープやハタガネなどで固定します。
この水平器を取り付けた1m80cmの板の両端に小さなL字金物を固定して本体の出来上がり。
この板を自分の目の高さに水平に置くことができれば、板の両端につけたL字金物の先端どおしを目で見通して、目標地点に立てた「バカ棒」を見ることにより、そこの地盤高さ(高低差)を知ることができるというわけです。
板を目の高さに水平に置くためには、私は片方にキャンプ用テントのポールを立てて板の片方をそこに固定し、もう片方をカメラの三脚に上に乗せました。
カメラの三脚は、ハンドルを回して高さを調節できるので、水平器の気泡を確認しながら板を水平に持っていきます。
この簡易レベルを使って、地盤高さを知りたい箇所に次々に「バカ棒」を立てて見通し、バカ棒に印をつけます。
印と印の差が即ち地盤の高低差
土を掘り下げるときは、これで時々確認確認しながら、印と印が同じ位置に来るまで掘っていくというわけです。
整地で大雑把に土を掘り取るときは、この簡易レベルで十分役に立ちました。
遣り方をかけたり、水糸を張る必要もないから、邪魔なものがない広々空間でバックホーなどを動かせます。

自作簡易レベルの精度
さて、こんな原始的な道具で水平確認の精度が出るのか?
後で「水」を使って正確に出した水平と比較して見ると、10メートル以内の測定範囲内で誤差は5cm以下程度でした。
5cmって大きな誤差じゃん!! とお思いでしょうが、整地・荒掘り段階ではそんな程度で十分です。
なにしろ石ころひとつでも5cmくらいありますからね。
機械で掘るときは深く堀過ぎるのは禁物なので、どっちみち最後には人力で所定の深さまで掘り下げます。
そのときはすでに「水」で正確に測って張った水糸を基準にするから大丈夫。
オートレベルがあれば最初から最後までオートレベルで水平確認が出来ますが、高価な道具を持たない個人のセルフビルドでは、
1、荒掘り段階では精度はイマイチだけど機動性の良い「手作り簡易レベル」を使い、
2、最後の仕上げは「水」を使って正確に出した「遣り方」と「水糸」を基準にする。
・・・というあたりが丁度良いかな、と思っています。この方法、私が実証済みですのでお勧めできますよ。♪
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。
元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)
第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。