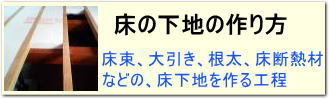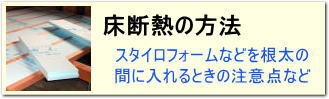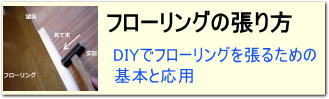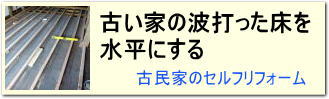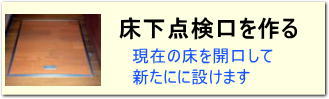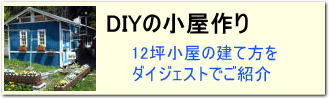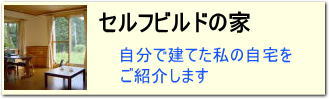床の補強

ピアノや蓄熱暖房機などの重量物を置く場合、その部分だけでも通常より床の強度が必要になることがありますよね。
そういうときに自分で(DIYで)床を補強する方法があります。 特別な技術・経験は不要で、床下に潜る勇気(?)さえあれば誰でもできますよ。♪
このページでは、1階の床を補強するための方法と、私が実際に床下に潜って重量物の直下の床を補強した事例を解説します。
床補強の方法 4種
ピアノや蓄熱暖房機などの重量物を置くためには、床を補強したほうが良いわけです。
では、そもそも床の補強にはどういう方法があるかというと・・・
- 根太のスパンを狭くする
- 根太のピッチを狭くする
- 根太や床板を、太く厚いものにする
- 重量物の直下に床束を配置(追加)する
これら1~4の方法について詳しく見てみましょう。
根太のスパンを狭くする
スパン=支点間の距離。つまり床の場合は根太が乗る大引きのピッチ(=設置間隔)に相当します。
一般的な木造住宅の1階床の根太のスパンは3尺。つまり909ミリなんですが、これを例えば2尺(606ミリ)とか1尺5寸(455ミリ)などにしてしまえば、それだけ床は強く(たわみにくく)なるわけです。
根太のピッチを狭くする
つまり隣の根太との間隔を狭くする。言い換えれば根太の本数を増やすということ。
一般的な木造住宅の1階床の場合、根太のピッチは、畳の部屋なら1尺5寸(455ミリ)、合板下地のフローリングなら1尺(303ミリ)。
これを、知り合いの家ではピアノを置く部屋の根太のピッチを1尺の半分、約150ミリにしていました。

これは私のセルフビルド自宅1階の、ピアノ部屋の床下施工の様子です。
ほかの部屋は標準どおり、根太のスパンを3尺、根太のピッチを1尺にしているのですが、ピアノ部屋だけは根太のスパンを2尺にしました。
大引きのスパン、即ち床束の間隔も、普通は3尺のところを、ピアノ部屋は2尺にしています。
ここにグランドピアノを置いていますが、十分な強度が得られていると思います。
根太や床板を、太く厚いものにする
スパン3尺の場合、根太の断面寸法は一般的に45×45や、45×60が多く使われていますが、これを例えば大引きと同じ90×90にすればかなり強力な床になりますね。
床板の下地も、一般的な厚さ12ミリの下地合板ではなく、厚さ24ミリや28ミリのネダレス合板にすれば当然強くなるわけです。
ネダレス合板なら断面に実(さね)がついているのでその点も有利
重量物の直下に床束を配置する
床束の本数を増やすわけだから、「根太のスパンを狭くする」と同じことなんですが、部屋全体を補強するのではなく、
蓄熱暖房機を設置するような、局所的な補強だけすれば良いケースのときは、この方法が一番現実的で理にかなっていると思います。
それに、上記の1~3の方法は新築時にやるならいいけど、後付け(リフォーム)で行うならば既存の床を一旦壊して作りなおすなどの大規模な工事になります。
その点、この方法は建てた後からでも、いつでも簡単に施工可能なところがgood
床下に潜って補強したい場所の直下に床束を立てるだけなので簡単!
つまり・・・
後付けで床補強するなら、断然! 4の『重量物の直下に床束を配置(追加)する方法』が適していると言えるでしょう。
後から床を補強する方法
床下に潜って床束を配置し、床を補強した事例
わが家に蓄熱暖房機を入れることにしたので、床下に潜って、床束を配置しました。
後から入れる床束は、高さが自由に調節できることが必要なんですが、それが可能なのはプラスチック製のプラ束か、金属製の鋼製束
わが家は新築時にプラ束を使ったので、今回も同様にプラ束使用です。 長さによって違うけど、だいたい1本千円~で買えます。
これがわが家の蓄熱暖房器。 熱容量7000VAで、重量が379kgもあります(驚!)
床下に潜り、床束(プラ束)を設置
床下点検口から床下に潜り、匍匐前進しながら蓄熱暖房器設置予定地の場所まで進みます。(^_^;
その直下の床下を、このように補強しました。↓

プラ束を根太に直接当ててもいいけど、荷重が均等に分散するよう、根太とプラ束の間に板をかませています。
板はツーバイ材の2×10材を使用
もちろん、プラ束は根太の直下にくるように配置
プラ束は(鋼製束も)高さ調整ができるので、土間コンとあて板の間をしっかり突っ張ったところでストッパーを締めて固定します。土間コンと接する面には専用接着剤使用です。
この狭いエリアに6本入れました。 十分過ぎるでしょう (^^)v
プラ束には2種類のタイプがある
プラ束には『台板タイプ』と『受座タイプ』があります
台板タイプ

『台板タイプ』は上端についている厚めの合板の下から、上に乗る大引きなどの木材にビス留めして固定するもの。
今回使用したのがこのタイプ。 角材だけでなく、巾広の板なども支えることが出来て便利です。
受座タイプ

『受座タイプ』は上端の「コの字」に大引き材などを受け、コの字の側面ビス穴から釘やビスを打って固定するもの。
大引きなどの角材に取付けるなら、このタイプが便利。
上記2タイプがあるので、状況に応じて使い分けます。
適用できる高さの範囲によって商品が違うので、適用高さも確認します。

わが家の既存のプラ束は大引きの下に配置しているので、受座タイプを使っています。
参考動画 鋼製束の取付け方
(鋼製束の取付け方)
↓↓↓
蓄熱暖房機を設置した
床補強が終わったので、いよいよ蓄暖を受け入れますよ~
業者から事前にもらっていた図面をもとに、背面固定のための下地木材をセットしておきました。
暖房器到着
中身はこんなふうに、電熱線がたくさん通っています。
そこへ投入される蓄熱レンガたち
これが重さの原因なんだよね
電熱線をはさむように、隙間なくレンガが積まれていきました。
重さ379kgの蓄熱暖房器 設置完了!
ばっちり床補強しているので、周辺を歩いてもビクともしません (^^)v
床下で安全に作業するために
床下は一般的に暗いので、潜って作業するためには、出来るだけ明るくて、尚且つ持ち運びやすい照明が必要です。
うちでは脚付きのハロゲンライト作業灯を使っています。
小さくて持ち運びやすく、地面に置きっぱなしでも安定するし、なにより凄く明るいので、床下に潜っても遠くの方まで照らしてくれます。
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。