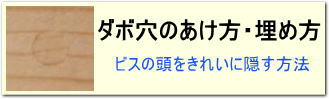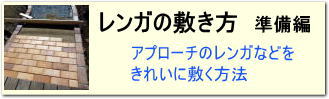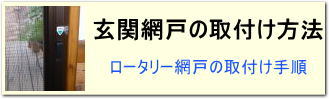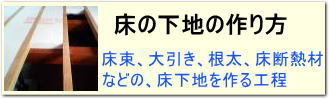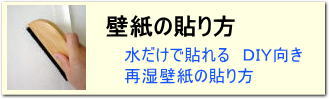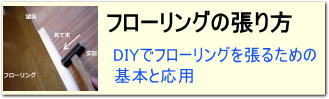玄関を作り、タイルを貼る DIYでタイル貼りの玄関を作っちゃおう

玄関タイル貼り施工中の一枚
(割付を確認しているところです)
このページでは、合板下地の玄関に300角のタイルを貼る工程と、玄関そのものの作り方について紹介します。
ビフォー・アフター
タイルを貼る前の状態がBefore
上がり框や巾木など、玄関に必要な部材を取付け、タイルを貼り終えた状態がAfterです。


玄関というと、普通の新築住宅ではコンクリート土間の上にタイルを貼っていくパターンが多いですが、うちでは他の部屋と同様に、根太の上に合板を敷いたものを下地としてタイルを貼っています。
他の部屋がフローリングのところを、タイルに置き換わっただけ・・・という感じ。
もちろん、床レベル(高さ)は玄関のほうを10cmほど低くしていますけど、その違いだけです。
この施工方法はとても簡単なので、セルフビルドに向いていると思います。
使用上も全然問題ありませんよ。
(^^)v
タイルの選び方と、使用したタイル
タイルには、どんな場所に使えるかという適正表示として、
1、屋内壁 2、屋内床 3、浴室床 4、屋外壁 5、屋外床 6、耐凍害適正
という種類があり、1 → 6 に行くに連れて耐久性が求められる感じです。
今回購入したのは、上記1から6まですべてに適していて、特に屋内壁、屋内床、浴室床、屋外床には◎の表示でした。
イタリア製の磁器質タイルで、サイズは、厚さ10mmの300角。ほぼ30cmの正方形です。

色調はライムストーンというものらしく、少し白っぽいテラコッタ調といった感じです。
天然石の風合いがあり、色調も自分の好みにぴったりでした。(^^)
使用するのは屋内床なのでもちろんOK。 浴室床にも◎で適するようなので、多分、耐久性は十分なのでしょう。
その分、お値段も張りますが (;゜д゜) アウトレット品としてタイル専門店で通常価格の半額以下で出品されていたものをゲット!
タイル貼りの手順
合板下地の玄関床に、300角のタイルを17枚分ほど貼り付けた作業手順です。
割付けを考え、あらかじめタイルをカットしておく
貼る場所(玄関床)にタイルを並べてみます。 この段階ではまだ接着剤を塗らず、ただ単に置いてみるだけです。

目地の巾も見込んで、完成形をイメージしながら並べてみます。
当然、寸法的に端数が出ると思うので、寸法を測ってあらかじめタイルをカットしておくわけです。

こんなふうに出っ張りのあるところもキチンと寸法を測り、タイルに欠きこみを入れておきます。

ディスクグラインダーにダイヤモンドカッターを装着してタイルを切ります。

全部並べて見たところです。
これを確認したら、いったんタイルをすべて取り外しておきます。
なぜ先にこれをやるかというと、接着剤を使う作業を始めてしまってから、端部の寸法をその都度測ってタイルをカットするのでは段取りが悪いからです。
効率が悪いし、モタモタしてると時間がかかり、貼る前に接着剤が固まっていったらヤバイので、焦らず確実に仕上げるには、あらかじめこのように準備しておいたほうが安心。
下地に接着剤を塗り、タイルを貼り付ける
下地(合板)のゴミなどをきれいに掃除し、よく乾燥させてから、接着剤を出します。

床面の何か所かに分散して出せば良かったけど、まとめて出しちゃったので失敗でした。
けっこう粘着性が高くてドロンとしてるんだよね~ (-_-;)

板切れなんかでおおまかに伸ばし、仕上げに「くし目ゴテ」で均等に塗り広げてみました。
写真では周囲に何も貼っていませんが、マスキングテープを貼って養生しとけば良かったです。(^_^;
接着剤が付くと面倒なんで・・・
ちなみに今回は床面全部を一気にやりましたが、もしも面積が広いなら、タイル貼りの際の足の置き場のこととか作業時間のことを考えると、2平米くらいずつに分割して塗ったほうが良いと思います。

タイルを置き・・・

ゴムハンマーで叩きながら、揉みこむようにして圧着させます。
この後、接着剤が完全に乾燥するまで作業中断。
以降は明日やることにします。
ちなみに私は使いませんでしたが、よりきれいに目地巾を揃えるためのグッズも市販されています。
目地を入れる

バケツに目地材を入れ水で練って程良い軟らかさにしたものと、ゴム鏝、スポンジを用意。

目地に、ゴム鏝を使って目地材を詰めていきます。
端っこは、巾木にどうしても目地材が付着してしまうので、マスキングテープで養生しておくと良いでしょう。

全部に詰め終えた状態。
目地巾より、かなり無駄にはみ出てしまいました。 まっ・・・素人なんで、こんなもんでしょう。(^_^;
はみ出た目地材を拭き取って完成

余分にはみ出た目地材を、スポンジを水で濡らしながらひたすら拭き取り。
根気が必要です。あまりゴシゴシやって目地に詰めた目地材まで拭き取ってはまずいので、丁寧にやります。
これが今回の作業で一番大変でした。(-_-;)

ふぅ~~ なんとか出来がりました。
左官系の作業はもともと苦手で嫌いだけど、今回も悪銭苦闘でした。
でも終わってみると、なかなか綺麗に仕上がったようで、満足満足 (^^)
床タイル貼りに必要な材料と道具
床タイル貼りに必要な道具や資材は、タイル本体以外では次の通り。

タイル貼り用接着剤
タイル貼り専用の接着剤。
特に下地が合板などの場合は、ある程度下地の伸縮に追随できるようなものを選定しています。
今回使用したのは変性シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で、硬化後もゴム状の弾性力を持つタイプです。
くし目ゴテ
接着剤を下地に薄く均一に伸ばために必要。
くし目状になっているので、接着剤が細かく凹凸のついた状態で一定の量と高さに揃えることができます。
なお、反対側は普通のヘラとして使えます。
なお、接着剤はけっこうドロッとしており、均す時にいきなり小さ目のヘラを使うと汚れるので、まずは板の切れ端などがあると便利でした。 板の切れ端でおおまかに均してから、くし目ゴテで仕上げるという感じです。
ゴムハンマー
接着剤の上にタイルを置いた後、コンコン叩いて馴染ませるときに使います。
普通の金槌だとタイルが割れるおそれがあるので、ゴム製のハンマーが便利。
タイル用目地材
水で練って、ゴムコテを使い目地に埋めます。
目地材はカラーもいろいろ出回っているので、タイルとの相性を考えて選ぶと良いでしょう。
ゴムコテ
タイルの間に目地を詰めるために使います。
ゴム製なので、金属製と違ってゴシゴシやってもタイルにキズがつかないので便利。
スポンジ
はみ出た、余分な目地材を拭き取るのに使います。
大きい方が使いやすいと思いますが、私の場合は3個セット100円で売られているような食器洗いスポンジを使っています。これで十分用が足ります。
ディスクグラインダーとダイヤモンドカッター

タイルを切るには、専用工具としてタイルカッターというものがありますが、わざわざそのために購入しなくとも、DIY作業全般に活躍するディスクグラインダーを持っていればOK。
これにダイヤモンドカッターを装着すれば簡単にカット出来ますよ~♪
タイル以外にも、レンガやブロックなども切れるので、一家に一台あると便利(?)
( 付録 )
玄関の作り方(DIY向き)
玄関というものは、本格的に作ろうとすると、上がり框(あがりがまち)や巾木(はばき)、玄関ドアとの納まりなど、けっこう難しい要素が多くて難易度が高い部類に入ると思います。
そういうわけで、私の取った方法は
最も単純・簡単で難易度の低い、DIYでも十分可能なやり方でしたので、ご紹介したいと思います。
自分で家を作る場合の参考になれば嬉しいです。
なお、わが家では玄関を仕上げるのが、セルフビルドの一番最後の工程になりました。
玄関を先に仕上げてしまうと、工事用に何度もそこを往復するから汚れてしまうことを恐れたためです。奥から仕上げて、入り口は最後・・・という感じ。
住みながらの作業となりました。(^_^;
下地は普通の部屋の下地と同様
ハウスメーカーが建てるような一般的な住宅の場合、基礎工事の段階で玄関部分はコンクリートで下地が作られていることがほとんどで、その上にタイルなどを貼るという作りだと思いますが、
私の取った方法はコンクリート下地ではなく、木材である根太の上に合板を貼るという、普通の部屋と同様の下地です。
ただし、玄関なので、部屋や廊下の床面より10cmほど低くなるようにしています。

玄関ドアはかなり以前に取り付けていますが、その段階で、玄関床の仕上がり面がドア開口部の下端と高さが一致するよう、設計段階で考えておきます。
玄関床面の周囲は、上り框や巾木を取り付けるので、まずは上の写真の状態から、上がり框や巾木などの「見切り材」を作ります。
見切り材(巾木や上がり框をなど)を作る

材料はありふれたワンバイフォー材やツーバイ材。
セルフビルドなので、特にこだわりが無ければどんどん経費節約しちゃいます。(^^ゞ
塗装は、水性ステインを2回塗りした後、水性ウレタンニスで仕上げます。

水性ステイン1回目が乾燥したら、サンドペーパー#240位で軽くサンディング。
これをやらないと、仕上がりがガサガサしちゃいます。

1回塗り後と2回塗り後の状態がよくわかる写真です。
2回塗りが乾燥したら水性ウレタンニスを塗り、これが乾燥したら、各パーツの所定の長さにカットして準備完了。
巾木や上がり框などを取付け

まずは玄関ドア左右の下地枠に取り付けましょう。
下地枠に接着剤を塗り、今作った仕上げ枠材を圧着してやります。
接着剤は普通の木工ボンドではなく、もっと強力な床用接着剤を用いました。
フローリングを貼るときに使うものと同じです。

こういう箇所は、突っかえ棒が使えるので良いですね。
もちろん、材料にキズがつかないように当て木をかましてから、突っかえ棒の端をコンコン叩いて圧着させます。

巾木についても突っかえ棒方式が使えるので、同じやり方で固定。

上がり框の場合は、対岸に強固な支点を確保できないので、突っかえ棒方式が使えませんでした。
しかたないので、最も一般的な木材固定方法である、ダボ穴あけ → ビス打ち → ダボ埋め の方式でいきます。 もちろん接着剤は同じように使います。
なお、上がり框はワンバイ材だと流石に貧相過ぎるので、やや厚みのあるツーバイ材としました。
それでも一般的な住宅の上り框より薄いと思うけど・・・(^^ゞ
なお、市販のツーバイ材は少し面取りしてあるので、廊下のフロアと接する面だけ自動かんな盤に掛けて面を取り去っています。( そうしないと廊下のフローリングとの間に凹みの溝ができちゃう。)
その作業が面倒な場合は、最初から面のついていない集成材などを利用すると良いでしょう。
ちなみに、上の写真に写っている上り框の下に挟んである新聞紙は、高さの微調整用のものです。
上り框の天端と、廊下のフロア面をピタッ!と揃えるために、上り框は玄関下地合板よりほんの少し浮いた感じになってます。
高さを完全に合わせる方法としては、上り框材を削って揃えるよりも、下地合板側を少し下げて、今回のように上り框材を少し浮かせて取り付けるほうが、はるかに簡単だからです。
設計段階で考えておきます。
さて、ダボ穴を埋めた箇所が目立たないようにするために・・・

ダボ穴を埋める「埋め木ダボ」の頭部が周囲と全く同じ色相になるよう、埋め木に使う材料もその塗装も、母材と同じ方法にします。
なので、同じ方法で作った巾木などの切れ端から、埋め木ダボを削り出しました。
市販の「木ダボ」なんか使ってしまうと、その部分だけ黒く目立っちゃうからね・・・

ダボを傷つけないよう、当て木をして慎重にダボ穴に打ち込みます。
これにて上り框の取り付け完了。 あとは前述のとおりタイルを貼り付けて玄関の完成となります。
(^_^)v


玄関が完成しました。(^^)v
以上、玄関作りについてでした。
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。