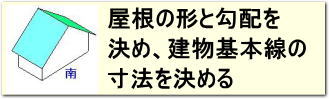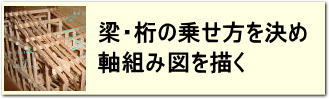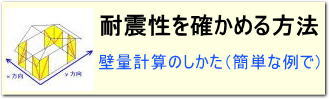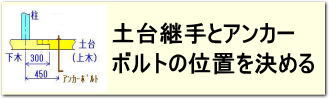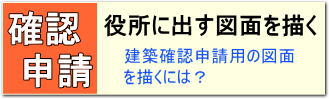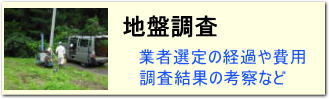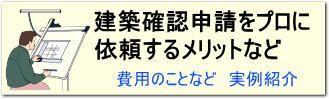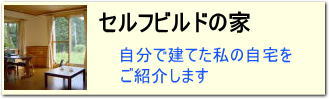自分で木造建物を設計する手順 第1章 柱や壁の配置
自分で家を建てることは、技術的にはそれほど難しいことではありません。
でも素人は経験がないし、専門の道具や資材がないこともあって、作業能率は悪いです。
しかし、だからといって出来ないわけではなく、無いなら無いなりのやり方があるのです。
このコーナーでは、一般個人が木造建物をセルフビルドするための設計のノウハウを書いています。
非常に単純なモデルとして、 2間×4間の8坪(16畳)のワンルームの家をつくることを想定し、設計を進めてみます。
全くのゼロからスタートして、家の設計図を描くまでの道のりを解説します。
工法は木造軸組み工法、いわゆる在来工法です。
「在来工法って木材に複雑な継ぎ手を刻んだりするやつでしょ。 そんなのとても無理」
・・と思わないでください。 やってみると意外に出来るもんです。
正確にピタリとうまく加工するためのコツがあります。 分かってしまえば「なあ~んだ!」 というようなことです。
これから行なう設計の手順は以下の目次のとおりです。
はじめに
例外的な地域を除いて、延べ床面積が10平方メートルを超える建物をつくる場合は建築確認申請が必要ですが、これから設計する建物は 2間×4間 つまり 3.64 × 7.28 = 26.5 平方メートルなので該当します。
でも建築士法では、木造建物で延べ床面積100平方メートルまでは無資格者が設計しても良いことになっているので、この建物は素人が設計図を描き、自分で申請してもOKなのです (^o^)
木造建物を設計するって、どこから手をつけて何をすればいいのか? では、手順を追って・・・
※ 家の設計図は建築確認申請に必要なもの以外にも多くの種類があります。
実際に施工する際に必要になるもので、施工図とも呼ばれていますが、でもここでは、とりあえず建築確認に必要な「平面図」「立面図」を描くまでを取り上げます。
その前に確認しておきましょう。
そもそも、建物の「面積」って何?
建物には「壁」があり、「壁」には厚みがあります。「壁」の中には軸組み工法の場合は「柱」が入っています。
建物の面積とは、「柱の芯」を結んだ線で囲まれた面積のことです。
決して、建物の一番外側の外壁で囲まれた面積ではないのです。
この場合の「2間(3.64m)」とか「4間(7.28m)」というのは、上の図でいうところの赤い線の長さということになるわけです。
1 柱の位置を考える
柱と柱の間に筋交いが入ることを考えると、柱と柱の間隔は1間以下がいいです。
一般的には
①1間(6尺)(=1820mm)
②4尺5寸(=1365mm)
③3尺(=910mm)
・・のうちから選びます。
今回はまず1間間隔で、仮に置いてみましょう。
という感じで、東西方向が4間、即ち7メートル28センチ、南北方向が2間、即ち3メートル64センチの家ですが、例えば1間、即ち1メートル82センチ間隔で柱を配置するとこうなります。
でも普通はこのままでは行きません。たいていは必ず修正が入ります。とりあえず描いてみました。
2 窓やドアの位置を決める
この平面図モドキに、窓や玄関ドアを希望の位置に配置してみましょう。
南側は窓を大きく取りたいし、東西には小さめの窓を1個ずつ配置して、北側も少し大きめの窓を配置することにしたとします。そして玄関ドアを南側に設けたとします。
3 柱の位置を再配置し、耐力壁の位置を決める
この案だと東側と西側の窓をはめ込む位置で、柱が邪魔ですね。この柱は移動しましょう。
窓をはさみ込むようにして柱を2本にします。
また、南側の大きな窓をはめ込む位置でも柱が邪魔です。
でもこの場合、ここの柱を取り去ってしまうと、梁をかけるときにいろいろ面倒になるので、ここは柱はそのままにして、窓を2つに分割することにします。
窓が入らない区間には、1尺5寸(=455mm)間隔で間柱(まばしら)を入れます。
1尺5寸というと、1間(6尺)の丁度4等分なので、1間間隔で立っている柱の間には、間柱が3本立つということです。
これで、柱や窓の位置が決まりました。
次に、耐力壁の位置を決めます。
木造軸組み工法では、地震や風の力で建物が水平方向に歪むことを防ぐため、斜めの部材である筋交いを壁の中にバランス良く配置する必要があります。
窓やドアが入る区間には筋交いを入れることが出来ないため、筋交いを入れる耐力壁は必然的に窓がない区間ということになります。
筋交いを入れる壁の区間は次のとおりとします。
建物の四隅の柱に取り付く壁は耐震上特に重要なので、ここに耐力壁をもってくるのが望ましいのです。
今回の例では、窓を壁の真ん中付近に持ってきたため、耐力壁は建物の四隅にうまく配置されました。
次は屋根を決めてみよう♪
次へ ⇒ 屋根の形と勾配を決める
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。
元岩手県の技術系職員(森林土木・木材関係)
第二種電気工事士、DIYアドバイザー、林業改良指導員及びバックホー等の重機運転資格が有ります。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。