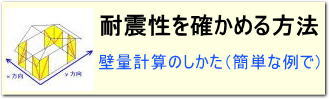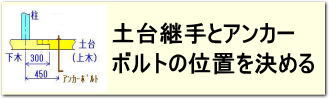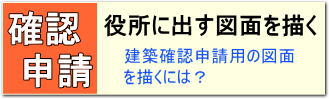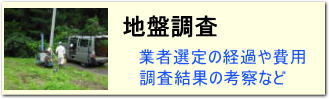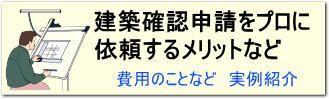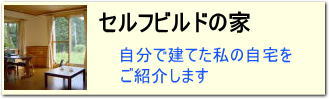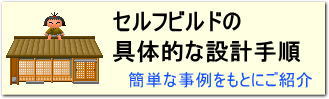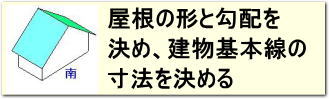自分で木造建物を設計する手順 第3章 梁と桁の乗せ方を決め、軸組み図を描く
6 梁と桁の乗せ方を決める
梁と桁 部材の名称など
梁(はり)も桁(けた)も横に架ける部材ですが、その違いは分かりますか?
まずはこの写真をご覧下さい。これは私が自宅を設計する際につくった軸組み模型の一部です。
屋根の重さをどのように支えているか、この写真で説明します。
- 屋根に一番近いのが垂木(たるき)です。直接屋根の重さを受け止めています。
- この垂木を受けているのが母屋(もや)です。垂木と直角に交差します。
- 母屋(もや)を、束(つか)という短い柱で受け止めます。
- そして束を受けているのが梁(はり)です。 母屋は高さがそれぞれ違いますが、梁の段階では束で高さを調整しているため同じ高さに並ぶことになります。
- 梁にかかる屋根の重さを柱で支えて、柱から土台~基礎コンクリート~最終的に地盤で全体を支えているわけです。
- さてここで、柱の上部を固定し梁と梁をつなぐ部材が必要です。それが桁(けた)です。
桁(けた)は梁と直交して、梁と同じように横に架ける部材ですが、屋根の重さを直接受けているわけではありません。 どちらかといえば上からの荷重を支える役割よりは、柱と梁をつないで軸組みを固定する役割が大なのです。
この辺が梁と桁の違いになります。(例外もありますが・・・)
梁、桁、母屋、垂木の構成
梁、桁、母屋、垂木の構成についても2つのパターンがあります。次のうちどっちにするか選びましょう。
- 母屋と梁が直交
- 母屋と梁が平行
母屋と梁を直交させるか、あるいは平行にするかは、屋根の勾配をどの方向に持っていくかということと、家の平面的な形に密接に関係します。
なにしろ梁は屋根荷重をうけるため太い材木になりがちですが、スパンが長くなればますます太い材料を使わなければならないため、梁のスパン(長さ)は出来るだけ短いほうがいいのです。
こうなりゃー、この例の家の場合は梁は南北方向に架けることでキマリ!
屋根勾配は東西方向ですから、垂木は東西方向。
母屋と垂木は必ず直交するので母屋は南北方向。
・・ということは、今回の例では母屋と梁が平行なタイプでいくということになりました。
梁と桁の乗せ方
これも大きく分けて2種類あり、
- 柱の上にまず桁(けた)を乗せてからその上に梁(はり)を乗せる・・・・「京呂組み」といいます。
- 柱の上にまず梁(はり)を乗せてからその上に桁(けた)を乗せる・・・・「折置き組み」といいます。
基本的にこの2種類に分類されますが、さらにいろいろなバリエーションがあって悩むところです。
ここでは、加工が比較的簡単で素人のDIYでも成功しやすく、且つ、強固な組みあがりになる「渡りあご」という仕口を利用したやり方で行きましょう。
これは私の自宅に採用したやり方で、加工方法には一部オリジナルの工夫も入っています。
加工精度の低い素人でも、失敗せずに強固な軸組みをつくることが出来る組み方です。
7 軸組み図を描いてみる
次のステップとして軸組み図を描いて見ましょう。
軸組み図というのは、建物の壁を垂直に輪切りにしたときの絵と思えばいいです。
梁と桁の載せかたが決まった段階で描くことができます。
とりあえず、寸法は無視して土台・柱・梁・桁・筋交いの配置を描いてみます。
軸組み図で大事なのは、筋交いをどのように配置するかということです。
地震や風圧力に対抗し、建物を構造的に安定させる役割をもつ「耐力壁」をどう配置するかは、すでに決めてありました。
この建物は東西南北すべての面の壁で、耐力壁は両側の四隅に面した位置に配置します。
図の「南面」では筋交いは両側に配置されます。
「軸組み図」を描いてみると、建物のイメージが大分沸いてきましたよね(^o^)
ではその他の壁はどうなるでしょう?
西面はこのようになりますね。
※ 東面は西面とほぼ同じだし、北面は南面とほぼ同じ(窓の位置が違うだけ)なので省略します。
次に、この軸組みで地震や台風に耐えられるか、計算をして確かめてみましょう。
次へ ⇒ 耐震性を確かめる
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。