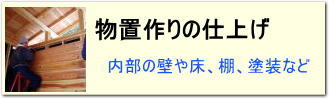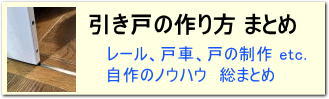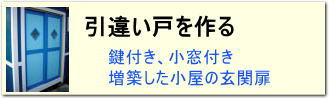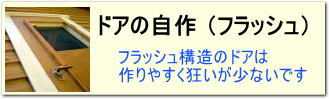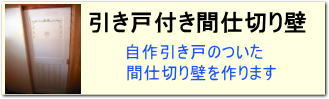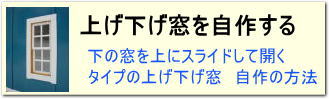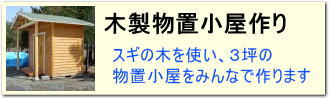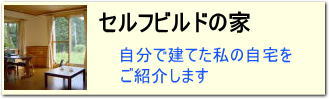木製建具(引き戸)の自作

木製物置小屋にふさわしいのは、やっぱり木製建具
というわけで、建具の自作は難しい部類に入るけれど、一番施行が簡単で、かつ、材料費が激安で、そこそこカッコイイ(DIYっぽい、カントリーっぽい?)ものが出来そうな方法で作ってみました。
材料費は2枚あわせて1万円でした。(戸車・レール込み)
引き戸の概要
小屋の玄関に、巾900mmの引き戸を2枚つけます。
物置小屋ですから物をもって玄関を行き来することが多いわけで、ドアでは開口部が小さすぎると思われたから両開きの引き戸にしたわけです。
建具の構造には基本的に「かまち組み」と「フラッシュ」がありますが、今回は合板を使わず無垢材だけで作るため、かまち組みの構造です。 一応・・・(^^ゞ
かまち材となる枠の部分は、外材ですが2×6のSPF材を使いました。
中に入れる鏡板は、厚さ15ミリの杉板を本実(ほんざね)加工して上下4枚ずつはめ込みます。
かまち枠を作る

建具のかまち枠の材料。 ホームセンターで購入した2×6材です。
2×4(ツーバイフォー)材だと巾が89ミリしかないので少し物足りない。
2×6(ツーバイシックス)だと巾が140ミリあるので、割と重厚感のあるかまち枠ができそうと思いました。
ただし、ツーバイ材というのは結構反れたり捩れたりしているものが多いですね。(ホームセンターだからか?)
手押しかんな盤と自動かんな盤があれば、反りや捩じれを自分で取り去る加工が可能だけど、この時点では持っていなかったので、既存の材料をそのまま使うことにします。
だから、できるだけ真っ直ぐなものを選ぶため、かなり時間をかけて吟味して選んできました。それでも若干の反れや捩れはあります。

まずはすべての2×6材に溝を掘ります。
溝巾は鏡板の厚さと同じ15ミリです。 深さも同じく15ミリにしました。
平行ガイドをつけた丸ノコで根気よく数回切り目を入れます。 テーブルソーがあればもっと楽で正確なんだけど・・・


ノミで荒く掘り取ったあと、トリマーで溝の底をきれいに仕上げます。
トリマーにはφ10のストレートビットを取り付けています。
( 溝の幅と同じサイズのビットだと木くずの排出が悪くてやりにくい。 少し小さめのビットの方がやりやすい。)
トリマーにストレートガイドを装着したうえで、ビットの底が溝の底に、ビットの側面が溝の側面と合うようにセットし、ガイドを材料の側面に当てながら、両側面から削って往復します。

全部の溝切りが終わりました。
これらが木製建具の枠を構成する部材(かまち)になります。

かまち材は縦枠2本と横枠3本で構成することにしましたが、( つまり「日」の字型になるということ。) これは中間に設ける横枠の端部の加工です。
上下から杉板をはめ込みますが、横枠自体は両端部を縦枠にはめ込む構造です。
鏡板を作る

かまち枠の中にはめ込む材のことを鏡板といいます。
これには杉板を使用。 何枚か必要なので、合端の部分に本実(ほんざね)加工をします。
これもトリマーを使って地道に削っていきました。
写真は♂側を作っているところ。

こんなふうになりました。
♀側は、♂側の突起に合うようなサイズで溝を掘ります。
組立てる

かまち枠の溝に、加工済みの杉板をはめ込んで、建具本体を組み立てていきます。
かまち材と、中の杉板は、接着しません。
(木材の乾燥収縮にともない、自由に動けるようにするためです。かまち組みで扉を作る際の基本になります。)

最後の縦枠をはめ込んでいるところです。 あて木をして玄能で叩き込んでいます。

固定は120ミリのビスを使いました。
縦枠の横から打ち込むのですが、縦枠の寸法が140ミリなのでそのままでは届きません。
まずはφ12のドリルで60ミリくらい穴をあけて・・・


ロングビットを使ってビスを打ち込んでいるところです。
その後、φ12の丸棒を、木工ボンドをつけて穴に埋め込みます。(ダボ埋め)
ボンドが乾いたら出ている部分をノコで切り、さらにかんなをかけて出来上がり。

建具本体は、こんな風にできました。
アクセントに、杉の木の形をあしらった小窓をつけました。
戸車を付ける

縦枠の下には戸車をつけます。
ドリルとノミとトリマーを使って戸車が入るスペースを掘り込んで、釘で固定しました。
ここで気をつけたのは戸車を建具の中心線に沿って正しく固定すること。
下枠材の中心を通るように建具の下面全体に中心線を墨打ちし、そのラインにそって戸車を固定します。 ここでは、マイナスドラーバーを使って歪みを修正しながら、ラインに合わせて釘打ちしています。
戸車が中心線からズレていると、スムーズな開閉は出来ないでしょうから・・・
↓↓↓
建物本体への取付け
引き戸の床には引き戸レールをレール釘で固定して戸車で滑らせますが、引き戸上部は鴨居が必要になります。
鴨居そのものを自作するのは面倒なので、図のようにA材を取り付けた上にB材を固定しました。
当然、引き戸上部は鴨居の溝巾より若干狭い突起をつけるように加工しておきます。

現場に仮固定してみました。
小屋の室内側から見ると2枚の建具の合わせ目から不規則なラインの光が漏れてきます。
床面のわずかな凹凸や、建具本体の歪みなので、合わせ目がピッタリくっつかないので、一旦はずして修正します。
削るべき箇所にかんなをかけて仕上げました。
※ 今回は無垢材をそのままで「かまち枠」を作ったので、このようなわずかな歪みが出ましたが、無垢材でもきちんとかんな盤に掛けてから使うか、もっと簡単には「集成材」を使用すれば、歪みが出ることはほとんど無いです。

小屋本体と同じ塗装をしています。
取っ手は、カラマツの木片を取り付けただけです。

出来上がり!
うまく開閉しました。 (^o^)
なお、下の図のように、鴨居の溝の中央Aと、両サイドの床Bに、木片のストッパーをつけました。
これで引き戸を開閉したときに開きすぎて取っ手の部分がぶつかったり、中央より行き過ぎることを防ぎます。
使用した材料 (引き戸2枚分)
平成17年での購入実績です。
2×6材
38×140×3640 1本1450円を4本使用
杉板
15×180×2000 1枚200円を8枚使用
戸車
ステンレス製 1セット 1155円を2セット使用
引き戸用レール
真鍮製 1700ミリ 1本 630円を2本使用
レール釘
1袋 63円

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。