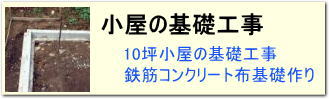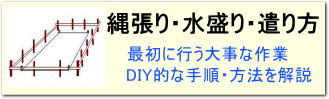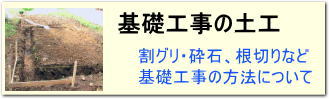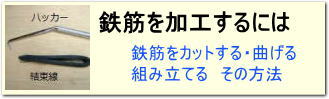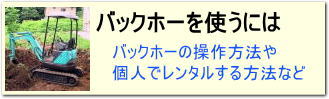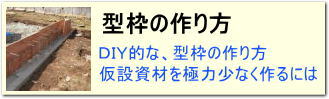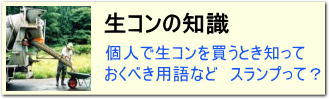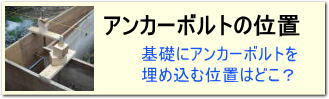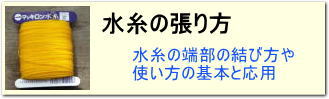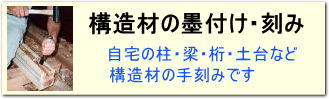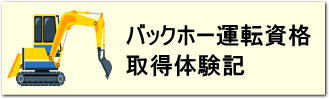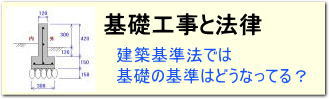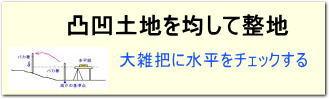基礎工事

DIYでの生コン打設の様子

DIYでの生コン打設の様子
DIYで住宅の基礎工事・・・家を建てるとき最初にする工事が基礎工事ですが、日曜大工のセルフビルドでは最も手を出しにくいと感じるのが基礎工事でもあります。
バックホウ(ユンボ)がないと土工事が大変。 コンクリートのことが良く分からないし、鉄筋の加工や組立なんかやったことない。
・・・・と感じるのが普通ですよね。
実際やってみると、バックホー(ユンボ)の運転も覚えたし、型枠の組立や鉄筋加工も出来ました。
私のセルフビルドライフ(?)の出発点が、平成6年10月からはじめた、この基礎工事でした。 ビギナーの作業なのでマズイところも沢山あります。
このページはあんまり参考にせず(笑)、より経験を積んでから行ったこちらの基礎工事の方も合わせてご覧ください。 いずれも鉄筋コンクリート布基礎です。↓↓
土工 ~ 鉄筋 ~ ベースコン打設まで

まず家の形に地面に縄を張り、その周囲に遣り方と呼ばれる丁張をつくります。
縄張りした線より一回り外側に適当な間隔で杭を打ち、「レベル」という水平を見る器械を借りてきて、すべての杭の同じ高さにマーキングをしました。この作業は2人以上でないとできません。夫婦共同作業でした。
マーキングした高さにあわせて、杭に板を打ち付け、歪まないように斜めに筋交い板を打ち付けます。これで遣り方が出来上がり。
家の外周などの各基準線と丁張り板との交点には釘を打ち、水糸を張って対角線の距離などを測り、遣り方の精度をチェックします。

「根切り」と呼ばれる床堀作業です。
リース会社からミニバックホーを借りて、UFOキャッチャーの感覚で楽しく掘ります。
冬に地面が凍結する深さ以上に深く掘っておかなければならないので、相当な量の土が掘り取られ、その置き場に苦労します。

荒掘り終了。
残土がうず高く盛られるので、作業手順をうまく考えてからやらないと、バックホウの居場所がなくなるのです。 (^_^;)
まわりにお堀が掘られた小山の上で、バックホウを運転するのはスリル満点です。

水糸を張って、逆T型のバカ棒を使って、深さや幅をチェックしながら、カッチャやスコップで人力床ならしをして整えます。
1日中これをやると、相当腰が鍛えられます。(^_^;)

砕石を投入します。
砂利屋さんからダンプで撒けてもらった場所から、ネコ(一輪車)で運んで投入します。
バックホウでネコに投入する際に、中心からずれると、ネコ(一輪車)が倒れて砕石が撒き散らかってしまいます。まさに、ゲームみたいなものです。
一人の作業なので、一回ごとにバックホウから降りて、砕石を運びます。

砕石は15cm厚さに敷き詰めて、リース会社から借りたランマで転圧します。
バックホウのレンタル料は一日8000円でしたが、ランマは1500円でした。
足先を転圧しないように注意!
(この写真は、後でつくった便槽まわりの基礎の際の状況です。)
この後、砕石層の上に、基礎フーチンの型枠をつくります。

鉄筋加工組み立て
鉄筋は13ミリと10ミリを使います。
「番線切り」の親分みたいな鉄筋カッター(知人から借りた)で切断し、折り曲げて、現場で組み立てていきます。

大勢の人手が必要なので、知人友人がたくさん助っ人に来てくれました。
途中の道が狭いので、生コン車は4トン車です。
雪で生コン車が滑って立ち往生し、あせりましたが、皆さんの協力でなんとか脱出させることができて、コンクリートが固まる前に打設し終えました。
この年はこれで作業終了! 長い冬を越して、来年、基礎工事後半に入ります。
でも実際には翌年、本業の転勤があってより遠くの街(現場まで車で2時間半)に引っ越したため、なかなか思うように工事を進めることができませんでした。 亀の歩みです(笑)
翌年、基礎コンクリートの立ち上がり部分をつくりました。
作業の流れは、・・・
残りの鉄筋を組み立てる ⇒ 型枠をつくる ⇒ ベースコンクリートの上に墨付けをする ⇒ 型枠を組み立てる ⇒ 生コンを打設する ⇒ コンクリートの養生をする
⇒ 型枠をはずす ⇒ 基礎天端にモルタルを塗って水平に均す
という具合です。その後、家の構造体、屋根、外壁下地が完成した時点で土間コンクリートを打ちました。
基礎コンクリート立ち上がりの施工

基礎の立ち上がり部分に鉄筋を配置していきます。
組み立てには、ハッカーというくの字型になった工具と、結束線という針金を使います。
Uの字型になっている結束線を鉄筋の交差部分に巻き、結束線のUの字部分にハッカーの爪を引っ掛けてクルクル回すと簡単に結束されます。

フーチン(ベース)の上に、型枠が立てられるラインを墨付けします。
「遣り方」どおしに水糸を張り、水糸の交点から下げ振りを降ろしてフーチンの上に基準点をつけます。
その後、墨つぼを使って全体に墨つけしていきます。

まず内側から型枠を立てていきます。
型枠はコンパネの両サイド際に桟木を打ちつけたもので、自分でつくりました。
墨線に沿って型枠をたて、下端はコンクリート釘で固定し、上は、斜めに杭を打って、杭に固定します。
水糸を張ってラインが曲がらないようチェックします。
コーナー部分は、はずす時のことを考えてつくらないと、後で苦労するのです・・(^^ゞ

内側と外側の型枠の間隔を、15cmに保って固定するために、丸セパという金具をセットします。
丸セパにも種類があり、長いのから短いのまで様々ですが、基礎コンクリートの巾(我が家の場合は15cm)にあわせた丸セパをセットします。
まず内側の型枠に電気ドリルで穴を開け、丸セパを通した後、外側の型枠をあててみて、現物合わせで穴を開ける位置をマーキングします。
写真に見えるように、100円ショップの洗面器はいろいろと重宝します。

現場でコンクリートを打設する場所まで生コン車が近づけなかったり、コンクリートを運ぶ距離が長い場合、生コンを打設するのに楽なのは、ミキサー車のほかにポンプ車も頼んで、生コンを圧送することですが、
ポンプ車を一台頼むと10万円はかかると知り合いから聞いたので、写真のようにコンクリートミキサー車から生コンを直接一輪車に落とし込み、一輪車で運ぶことにしました。

生コン打設(流し込み)
プロはバイブレーターを使いますが、持っていないので原始的に棒でつついて、型枠を外からゴム槌で叩き、生コンが均等に行き渡るようにします。
ここで手抜きをすると「ジャンカ」や「豆板」と呼ばれるボロボロの面になってしまいます。
少ない人数で、すばやくやらないと硬くなってくるので大忙しです。昼飯なし!
固まらないうちに、アンカーボルトを所定の位置に植え込んでいきます。アンカーボルトの位置がすぐにわかるよう、あらかじめ型枠には印をつけておきます。
アンカーボルトは、例えば土台の継ぎ手の♂側の端部近くに配置したりしますが、位置がずれるとヤバイのです。

助っ人Aの見事なコテさばき
まずは木ゴテで均します。素人だけどそれなりに出来るもんです。
この後、シートをかぶせて養生。

一週間後の日曜日に型枠を取り外し、まあまあ、うまくできていました。

基礎の天端を均すため、モルタルを水平に塗ります。
アンカーボルトには、ネジの部分にモルタルが付着しないようにガムテープで保護しておきます。
あらかじめ、基礎の側面に計画高マイナス5cmの位置に水平墨を打っておき、幅5cmの板で天端部分をはさみ、鉄筋を曲げてつくったものではさんで固定したうえから、モルタルを塗ります。
基礎コンクリートには、あらかじめたっぷりと水を打っておきます。
カナゴテで丁寧に仕上げます。
土間コンクリート

屋根を貼り、壁下地が出来た段階で、土間コンクリートをつくりました。
まずは地面を平らに均し、砕石を厚さ10cm程度敷きます。
砕石は一輪車(ネコ)で運んで、カッチャで敷き均しました。穴掘りしても敷き均しにしても、スコップを使うより楽です。

敷き厚さの確認は、土台天端からの下がり寸法を測ることにより行ないます。
写真のように、土台に引っ掛けるだけで確認できる冶具を、端材でつくっておくと便利 (^^)v
こうすることで敷き砂利の水平を(おおむねですが)簡単に取れます。

この段階で、基礎コンクリートにあけておいたスリーブ(穴)に排水管の塩ビパイプを通しておきます。
コンクリートに埋まってしまってからでは通せないですからねぇ・・

砕石を敷き詰めたら、レンタルしたランマでつき固めます。
ランマのレンタル料は一日1500円でした。 ハッチバックのクルマに積めますよ (^^)v
ランマはエンジンをかけると上下にピョンピョン跳ねるので、その様子を見た妻は笑い転げていました。そんなに面白いかな?
なお私はランマを使いましたが、「プレート」という、振動でつき固める機械の方が楽かもしれません。 プレートのレンタル料もランマと同じです。

例によって一輪車で生コンを運びます。
土間コンクリートの厚さは7cmとしました。
床下換気について書かれた本には、地面からの湿気を防ぐには防湿シートを敷いて砂で押さえるか、厚さ7cm以上の土間コンクリートを敷くかすればいいと書いてあったからです。
鉄筋は入れていません。無筋です。もし、ものすごく荷重がかかるものならば、今ではホームセンターでも売っているワイヤーメッシュを入れればいいでしょうが、その際には、砕石との間に空間をつくるためのモルタルブロックを置くなど細工が必要になると思います。

土間コンクリートのように広い面積に生コンを打つ場合、普通の木ゴテでは小さすぎて均すのが大変です。
現場の端材を使って写真のような大型のコテを自作しておくと便利です。
コテは普通の板でいいのですが、横に動かしやすいように端部の上の角を削って薄くしておきます。こうしないと、コテを横に動かしたときに生コンに引っ掛かってしまうのです。
コテで生コンを押し付けながら均した後、最後に長い板を使って全体に平らにすれば完了です (^^)v
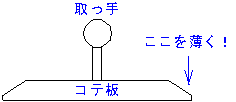
コンクリートについて
コンクリートは自分で作ることもできますが、住宅の基礎コンクリートともなれば量は膨大ですから私は生コンを買いました。
生コンは生コンプラントといわれる工場できちんと品質管理されて作られていて強度も信用できるので、住宅の基礎という大事な部分に使う場合は、強度・品質の面からも、労力の面からも、自分でコンクリートを作るより生コン工場の生コンを買う方がずっといいと思います。
生コンの価格は、配合にもよりますが1りゅーべ(立方メートル)当たり運搬費込みで1万5千円前後です。
生コンは、コンクリートミキサー車が工場を出てから、おおむね1時間半くらいまえに打設し終えないとまずいといわれており(時間がたつと固まる)、短時間で作業を終えるためには人手が最低4人くらいは欲しいです。
自分一人のセルフビルドといえども、このときばかりは家族・友人に声をかけましょう。
また、いくら工場から品質の安定した生コンを買っても、打設の際にきちんと振動を与えて型枠内の隅々まで行き渡らせたり、打設後もコンクリートが乾燥し過ぎないようきちんと養生することを怠ると、ジャンカと呼ばれるボロボロのコンクリートになったりクラック(ひび割れ)が発生しやすくなります。
自分で家一軒つくる過程では、基礎コンクリート以外にも便槽の蓋周りなどの少量のコンンクリートが必要になるときがあり、そのときは自分で作ります。
生コンの場合は、最低0.25 りゅーべ以上でないと売ってくれないようです。
生コンを購入するための知識については、こちらのページで詳しく解説しています。
⇒ 生コンの配合って何?
氏家誠悟(seigo uziie)
2004年からこのサイトを運営している個人です。自分で家2棟、小屋2棟をセルフビルドしました。「自分でわが家を作る本。」の著者です。

自分で住処を作れるようになろう!
DIYで本格的な木造建物を作る方法を、動画で詳しく解説したDVDです。 私の作品です。
ご自分で家を建てるために、きっとお役にたつと思います。